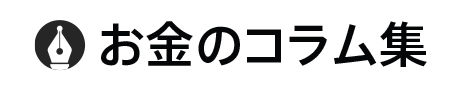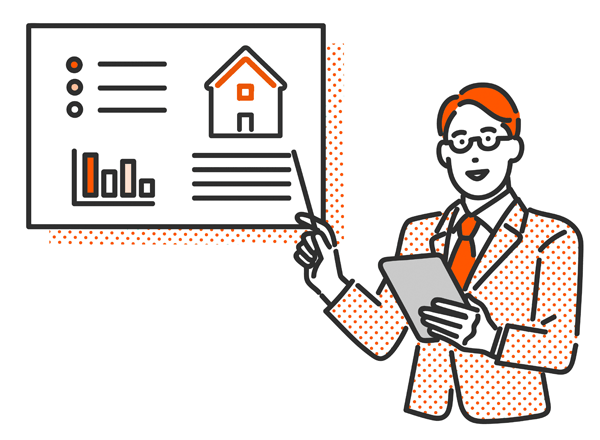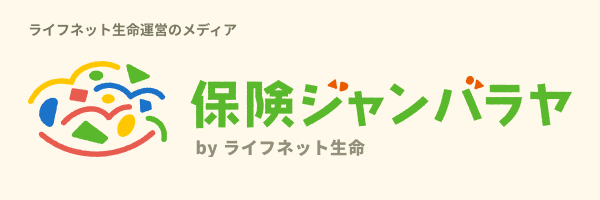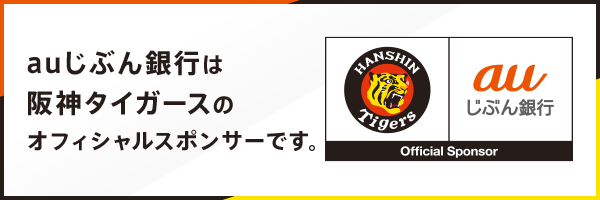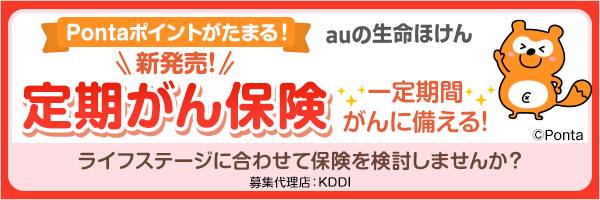住宅ローンの「がん団信」は必要?メリットや注意点について解説
監修者:新井智美(ファイナンシャルプランナー)
2025年2月14日(2022年7月14日公開、2024年3月21日更新、2025年2月14日更新)

「生涯でもっとも高価な買い物の1つ」といわれるマイホームの購入時には、多くの方が「住宅ローン」を利用します。教育費の捻出や、老後資金の準備も進めながら、借り入れた高額な金額を長い期間をかけて完済を目指していくことになるでしょう。
では万が一、住宅ローンの返済中に大きな病気に見舞われて働き続けられなくなった場合、どうすればよいのでしょうか。返済が難しくなった場合に強い味方となってくれる団信の1つに「がん団信」があります。本記事では、がん団信の概要やメリット、注意点について解説します。
「がん団信」とは
住宅ローンの返済中に契約者が死亡、あるいは高度障害状態となった場合、その時点での住宅ローン残高に相当する保険金が支払われ、住宅ローンを完済してくれる保険があります。これを団体信用生命保険(略称:団信)といいます。
ひと昔前までは、「死亡および高度障害状態になったとき」のみが保障の対象でした。昨今では、住宅ローン金利に所定の割合を上乗せすることで、「がん保障」もしくは「疾病保障」などが追加される団信プランが登場しています。まずは具体的な保障内容について確認してみましょう。
一般的に「がん団信」は、一般団信と同じく「死亡・高度障害」「余命6ヶ月の診断」の保障の他、「がん(所定の悪性新生物)」と診断確定された場合に保険金(住宅ローンの残債の一部もしくは全額)が支払われる団信です。
がん保障に特化している金融機関が多いですが、がん保障とあわせて、以下の保障がついている金融機関もあります。
- すべてのけがや病気(精神障害を除く)で一定の入院条件を満たした方を対象に、入院期間中の毎月の住宅ローン返済額相当(ボーナス返済額を含む)の保障を受けられる「月次返済保障」
- すべてのけが・病気(精神障害を除く)で一定の入院条件を満たした場合には、残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローンが完済される「全疾病保障」
「がん団信」には、住宅ローン残債の50%が保障される「がん50%保障団信」と住宅ローン残債すべてが保障される「がん100%保障団信」を取扱う金融機関があります(各金融機関によって団信の名称や保障内容は異なる場合があります)。一般的に、がん50%保障団信は金利上乗せがない金融機関が多く、がん100%保障団信は金利に年0.1%~年0.2%程度上乗せになる金融機関が多いようです。
一例としてauじぶん銀行では、がん50%保障団信、がん100%保障団信、がん100%保障団信プレミアムなどを取扱っています。金融機関ごとに保障内容や上乗せ金利はさまざまです。各金融機関のウェブサイトにて、詳しい保障内容や上乗せ金利などを確認してみるのもいいでしょう。
「がん団信」の必要性
厚生労働省の公表したデータによると、人口10万人あたりの死因の1位は「悪性新生物(腫瘍)」つまり「がん」で、全体の24.3%、およそ4人に1人の割合です(※)。
さらに、2位は「心疾患」、4位は「脳血管疾患」、9位は「腎不全(腎疾患)」(※)となっています。
こうした病気にかかると、亡くならなかったとしても、その後の闘病生活や離職によって家計に大きな負担を抱えるおそれもあります。
「がん団信」に加入していると、住宅ローン契約者の死亡リスクに加え、がんと診断されたときには治療費(給付金が支払われる場合)や住宅ローン返済の負担を軽減できるため、生存中の経済的リスクにも備えられます。
住宅ローンの特約は金融機関の取扱い商品ごとに異なります。情報収集を行い、保障内容をしっかりと検討することが大切です。
- ※厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況
 」より
」より
「がん団信」に加入する4つのメリット
「がん団信」に加入するメリットをみていきましょう。
保障金額はがん保険に比べ高い
「がん団信」の最大のメリットは、生命保険商品の「がん保険」と比べて圧倒的に高額の保障を得られることです。「保障額=住宅ローン残高(※2)」であるため、「がん団信」を付帯することで、一般的に数千万円単位の保障が得られることになります。
- ※2がん50%保障団信の場合、がん診断時の保障額は住宅ローン残高の半額となります。
一方、生命保険商品の「がん保険」では、がんと診断された場合に100万~数百万円程度の一時金が給付されます。さらに入院・通院、手術や抗がん剤治療など、特定の治療を受けるごとに給付金が加算されていくのが一般的です。治療が長くなると給付金の累計額は増えていきますが、かなりの長期療養でも数千万円単位の保障を得られることは稀でしょう。
また保険料負担の側面から見ても、団信の優位性は歴然です。住宅ローン残高1,000万円(35年返済)あたりの負担額(=保険金1,000万円あたりの保険料相当額)は以下の通りです。
- 「がん団信(金利上乗せ年0.2%)」の場合で月900円弱(※3)
- ※3細かな金利設定により負担額には若干の差が生じます。
一方、生命保険商品の「がん保険」では、診断給付金100万円に入院給付日額1万円を加えた程度の保障を組んだ場合(保険期間:終身)、以下のような保険料負担が必要(※4)です。
- 25歳は男女とも月2,000~2,500円前後
- 30歳男性で月2,500~3,000円前後、30歳女性は月2,000~3,000円前後
- 35歳男性で月3,000~4,000円弱、35歳女性は月2,500~3,500円前後
- ※4保険料は、保険会社や商品内容、被保険者の年齢・性別により異なります。
増加する「がん」、死因上位を占める「生活習慣病」リスクに備える
日本人の死亡原因のトップは「がん」です。次に「心疾患」、「老衰」、「脳血管疾患」と続いており、日本人の死亡原因の上位を占める「がん」「心疾患」「脳血管疾患」は、「3大疾病」と呼ばれます。これらの疾患は重篤であり、罹患すると長期の療養を要します。入院や通院などで就労に大きな制限がかかることから、大幅な収入減や失業も考えられ、医療費の負担も発生するでしょう。経済的困難と無縁でいることは難しいといえます。
昨今では、がん患者の治療と就労の両立を支援する取り組みが国を挙げて行われています。一方で、「がんの診断を受けて退職・廃業した人」は、就労者のうち17.0%(※5)を占めており、また、「退職後に再就職・復職を希望しながら無職である人」は20.1%(※5)と、必ずしもがんの治療と終了を両立できている方ばかりではないことがわかります。
- ※5厚生労働省委託事業「令和5年度調査患者体験調査報告書(速報版)
 」より
」より
(国立がん研究センターがん対策情報センター調査)
「がん団信」を付帯すれば、住宅ローンの返済を気にすることなく治療に専念、あるいは病状に応じて無理のない就労を選択できるでしょう。患者さん本人のみならず、闘病を支えるご家族にとっても大きな安心となるはずです。
入院やケガなど働くことが一時的に困難な場合でも保障される
先述の通り、「がん団信」には、重篤な状態には至らないものの、病気やけがによる入院で働くことが一時的に困難な場合に、住宅ローンの返済額相当の給付金を受けられる「月次返済保障」がついている金融機関もあります。
充実した医療サポート
金銭による直接的な給付だけでなく、「セカンドオピニオンサービス」や「24時間電話健康相談サービス」といった付帯サービスが受けられる金融機関もあります。医療や健康に関する情報を得られるのも、「がん団信」の大きな魅力です。
「セカンドオピニオンサービス」は、専任のヘルスカウンセラーによるガイドを経て総合相談医による意見をもらったり、優秀な専門臨床医の紹介を受けたりといったことが可能なサービスです。
「24時間電話健康相談サービス」は、経験豊富な医師や看護師・保健師が24時間・年中無休で電話による健康相談を受付けてくれるサービスです。日々の健康管理から、お子さんの深夜の急病にも専門家のアドバイスを受けることができるのは心強いでしょう。
「がん団信」プランの注意点
「がん団信」の契約にあたっては注意しておかなければならないポイントがあります。順を追って確認していきましょう。
申込時の健康状態や既往歴により加入できないことがある
団信も1つの保険です。申込時には健康状態や過去の病歴などを正確に告知する必要があり、内容によっては加入できないケースもあります。
保障の対象外となるがんがある
がんの保障のうち、「悪性黒色腫を除く皮膚がん」および「上皮内がん」はがん診断保険金の支払い対象から除かれます。
がんの保障については免責期間が設けられている
がん保障特約・がん診断給付金特約、上皮内がん・皮膚がん診断給付金特約・がん先進医療給付特約には、責任開始日からその日を含めて90日間の免責期間が設けられています。よって、その期間に保険金支払事由に該当しても、保障を受けることはできません。
プラン変更の際は再告知が必要
団信プランの変更を希望する場合は、健康状態について再度告知が必要です。告知内容に変更が生じている場合は、希望が叶わない可能性もあります。本審査の承認以降は団信プランの変更ができないケースがあります。また、住宅ローン融資後は団信プランの変更や中途解約はできません。
住宅ローンの月々の返済負担が増加する
保障の内容によっては金利上乗せが生じるため、月々の住宅ローン返済額の負担も増加します。返済期間が経過するごとに、支払い総額も増加していきます。
生命保険料控除の対象外
金利上乗せにより生じた保険料相当額については、所得税および住民税における生命保険料控除の対象とはなりません。
保険金の総額が徐々に少なくなっていく
「保障額=住宅ローン残高相当額」のため、返済が進み住宅ローン残高が減少するに従い、保険金の総額は徐々に少なくなっていきます。
契約できる年齢に制限がある
多くの金融機関では、「がん団信」に満50歳以下など加入年齢制限を設けています。
「がん団信」についてよくある質問
最後に、住宅ローンの「がん団信」プランを検討する際、よくある疑問や不安にお答えします。
Q1.「がん団信」とがん保険(医療保険)の違いは?
がんや心疾患などの疾病に罹患するリスクへの備えには、「がん団信」の他、がん保険などの医療保険(生命保険)へ加入する方法もあります。病気にかかったときのリスクへの保障という共通点はありますが、住宅ローンの特約と保険には違いがあります。
「がん団信」と「がん保険」の主な違い
| がん団信 | がん保険(医療保険) | |
|---|---|---|
|
加入目的 |
闘病中の住宅ローン返済への備え |
治療にかかる経済的負担への備え |
|
保険料 |
住宅ローンの借入金利に上乗せなし、または金利上乗せ(年0.05~0.5%ほど)が一般的 |
3,000~1万円ほど |
|
保障内容 |
住宅ローン残高の免除、診断給付金や入院給付金など |
診断給付金、入院・通院・手術給付金、放射線治療費など |
|
保障期間 |
住宅ローン返済中 |
ご自身で決めた契約期間 |
団信の特約は闘病中の住宅ローンの返済にかかる負担を抑えるもので、病気の治療を目的とした医療保険とは性質が異なる点に注意が必要です。
住宅ローン返済中にがんなどの疾病に罹患すれば、医療保険で治療に専念できても、住宅ローン返済の負担が重くなると予想されます。病気への備えを充実させたいなら医療保険にも加入しておくなど、それぞれの違いを理解したうえで上手に併用しましょう。
Q2.住宅ローンを借換えても保障を引き継げる?
住宅ローンを借換えると、付帯されていた特約の保障も終了します。
住宅ローンは、契約の都度、金融機関から審査を受けなければなりません。借換え先の金融機関でも、あらためて健康状態を告知のうえ、団信に加入することになります。
金融機関ごとに団信の保障内容は異なるため、以前の契約と同じ保障を受けられるとは限りません。住宅ローンの借換えを検討するときは、団信の保障内容もあわせて確認しましょう。
借換え時は、年齢を重ねた分、ご自身の健康状態が変わっている可能性も考えられます。告知にあたり、申告内容によっては加入できない場合もあります。
メリットと注意点をふまえた上で、ご自身にあった団信プランを検討ください
「がん団信」のメリットや注意点について解説してきました。上乗せ金利がある団信を選択した場合、「がん団信」は、住宅ローン完済まで保険金支払い事由に該当しなければ、上乗せ分の負担が掛け捨てとなってしまいます。
しかし、保険金支払い事由に該当してしまった場合のリスクの大きさを考えると、少額の負担で大きな保障を得られ、大きな安心感につながります。あらためて「全員のリスクを全員で支える」という保険本来の役割を見つめ直し、注意点なども踏まえながら、ご自身にあった団信プランを選択しましょう。