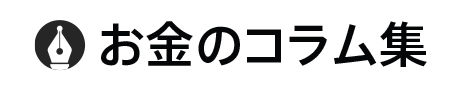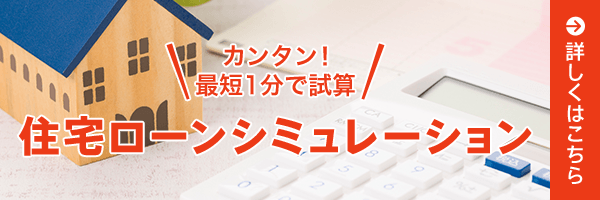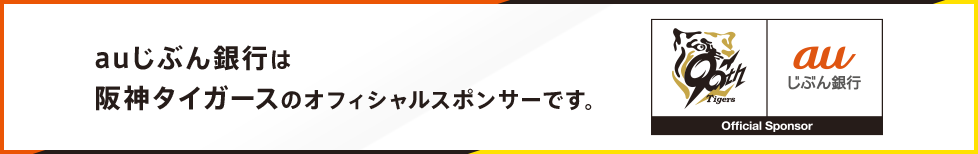2025/02/14(2023/12/20 公開、2025/02/14 更新)
年収800万円の人が組める住宅ローンの金額の目安|上限や適正借入額も解説
監修者:新井智美(ファイナンシャルプランナー)

自宅購入の際は、住宅ローンを利用する人が多い傾向です。住宅ローンを利用するためには、金融機関へ借入れの申込みをして審査を受ける必要がありますが、審査項目の一つに年収があります。
年収が800万円だと、どのくらいの金額を借入れできるのでしょうか。今回は、年収800万円の人が組める住宅ローンの金額について上限や適正な借入額について解説します。
年収800万円で住宅ローンを利用する際の借入可能額
一般的に住宅ローンで借りられる可能額は、年収の5~7倍程度といわれています。これに当てはめると年収800万円の人の場合、4,000万~5,600万円程度までの借入れが可能というわけです。また金融機関によっては、返済比率を基準にして借入可能額を算出するところもあります。
返済比率とは、年収における年間ローン返済額総額の割合のことです。ローン返済額には、住宅ローンだけでなく他社からの借入れも含めます。一般的には、返済比率が30%を超えると返済が困難になる可能性が高くなるといわれており、できるだけ20%程度に収めるほうがよいでしょう。
そうなると他社からの借入れがない場合、年収800万円の人の返済比率から算出できる年間返済額は160万円(800万円×20%)、月に換算すると約13万3,300円までということになります。
年収800万円の世帯に無理のない返済負担率
返済負担率は、年収を基準に計算しています。しかし実際の手取り額は、所得税や住民税、社会保険料などが引かれた額です。そのためより現実的な数値を考えるなら手取り額で計算する必要があります。手取り額は、年収や家族構成などによっても異なります。概算で収入の7割程度とイメージしておくとよいでしょう。例えば年収800万円の人であれば年間手取り額は560万円程度といった具合です。
返済負担率を20%と仮定するなら、年間返済金額は112万円(560万円×20%)、毎月の返済額は9万3,300円程度となります。無理のない返済を考えている場合は、年収800万円でも毎月の返済額は9万~10万円の範囲内にしておくことがおすすめです。
住宅ローン利用者の現状
実際に住宅ローンを利用している人は、どのくらいの金額を借入れできるのでしょうか。住宅金融支援機構が公表している「2023年度 フラット35利用者調査」によると、2023年度・全国の物件別の借入額と年収倍率は以下のようになっています。
| 物件のタイプ | 平均世帯年収 | 年収倍率 | 平均借入額 |
|---|---|---|---|
|
注文住宅 |
629万円 |
7.0倍 |
3,040万円 |
|
土地付き注文住宅 |
704万円 |
7.6倍 |
4,171万円 |
|
建売住宅 |
600万円 |
6.6倍 |
3,092万円 |
|
マンション |
955万円 |
7.2倍 |
3,889万円 |
|
中古戸建住宅 |
536万円 |
5.3倍 |
2,182万円 |
|
中古マンション |
659万円 |
5.6倍 |
2,393万円 |
参考:住宅金融支援機構|2023年度 フラット35利用者調査![]()
物件別に見ると年収倍率がもっとも高いのは、土地付き注文住宅を購入する人で7.6倍、平均借入額も4,171万円と高額です。次いで高かったのは、マンションの購入者で年収倍率7.2倍、平均借入額は3,889万円でした。また住宅を購入する人の多くが頭金を用意しており、物件価格に対する頭金の割合は約8~20%と物件によって異なります。
頭金を入れるメリット・デメリット
住宅購入の際に頭金をいくら用意するか悩む人も多いのではないでしょうか。ここでは、頭金を入れることのメリット・デメリットについて解説します。メリットとデメリットの内容を理解したうえで、頭金を準備するのか、準備するならどのくらいの額かなどを判断するとよいでしょう。
頭金を入れるメリット
頭金を入れることで得られる大きなメリットは、借入金額を少なくできることです。住宅ローンは、高額な借入れを行い長期にわたって返済していくため、借入金額が少なければその分総支払利息の負担を少なくしたり、総返済額を抑えたりする効果が期待できます。また、借入金額を少なくすることで、毎月の返済額を抑えることも可能です。
頭金を入れるデメリット
頭金を入れるデメリットは、手元資金が少なくなってしまうことです。例えば「住宅購入後に子どもの進学などでまとまった資金が必要」という人は、できるだけ手元資金を残しておきたいと考えるのではないでしょうか。頭金を用意することを考えるあまり、住宅購入のタイミングを逃してしまうことも考えられます。
住宅ローンの頭金の平均額
国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査」によると、2023年度の注文住宅の住宅建築資金(土地購入資金を除く)は全国平均で 4,319 万円となっています。そのうち、頭金は平均 1,261 万円で、自己資金比率は29.2%です(※)。
つまり、新築住宅を購入にあたって、頭金を3割ほど用意する方が多いとわかります。
先述の通り、住宅ローン返済の負担を抑えようとして頭金へ現金を投じすぎると、急な支出や家計状況の変化があったとき、手持ち現金が不足して困るおそれがあります。
「頭金は3割」はあくまで目安としておき、家族構成やライフプラン、貯金額などを考慮して、無理のない範囲で頭金に充てる金額を検討しましょう。
- ※国土交通省「令和5年度 住宅市場動向調査 報告書
 」
」
頭金の金額で返済額はどのくらい変わる?
実際に頭金を入れる場合と入れない場合では、毎月の返済額そして総返済額にどのくらいの差が生じるのでしょうか。以下の条件を仮定し、シミュレーションしました。
- 物件価格:4,000万円
- 金利年1.9%(全期間固定金利)
- 返済期間35年
- 元利均等返済
- ボーナス払いなし
| 頭金の額 | 借入金額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 利息負担額 |
|---|---|---|---|---|
|
0円 |
4,000万円 |
13万461円 |
5,479万3,602円 |
1,479万3,602円 |
|
400万円 |
3,600万円 |
11万7,415円 |
4,931万4,193円 |
1,331万4,193円 |
|
800万円 |
3,200万円 |
10万4,369円 |
4,383万4,787円 |
1,183万4,787円 |
- ※下記住宅ローンシミュレーターを使って計算
頭金を入れない場合、毎月の返済額は13万461円です。年収800万円の返済負担率以内には収まっているものの、手取り収入から考えると家計に負担がかかる可能性があります(前述の無理なく返済できる額9万3,300円よりは多い)。
また返済期間も35年と長いため、約1,500万円の利息を負担しなければなりません。しかし借入金額の1割の頭金を用意することで、毎月の返済額は11万7,415円(▲1万3,046円)まで減少します。
さらに2割の頭金が用意できれば、毎月の返済は10万4,369円(▲2万6,092円)となり、利息負担額も約296万円の差が出ます。住宅を購入する際には、事前にどのくらいの頭金を用意できるか、また頭金を用意することで毎月の返済額や最終的な利息負担がどのくらいになるのかをシミュレーションしたうえで判断するようにしましょう。
借入期間や金利タイプによっても返済額は異なる
住宅ローンの返済額は、借入期間や金利タイプによっても変わるため、どちらの要素も慎重に検討する必要があります。
例えば、借入期間を短くすれば毎月の負担は大きくなりますが、総返済額を抑えられます。また、契約時に低金利だった変動金利を選んだものの、その後金利が上昇に転じて返済額が大きくなる可能性もあります。
そこで、変動金利・固定期間選択型・全期間固定金利の3つの金利タイプごとに、返済期間の違いで毎月の返済額や総返済額がどれだけ変わるかを見ていきましょう。
- ※借入金額を4,000万円と仮定し、借入期間と金利タイプの違いでどのくらい返済額に差が生じるのかについて「auじぶん銀行のシミュレーション」を使って試算しています。
変動金利
変動金利とは、原則半年ごとに金利が見直される金利タイプです。3つの金利タイプのなかで金利が低く設定されているため、変動金利タイプを選ぶことで利息負担を抑えることができます。また見直された金利は、直ちに毎月の返済額に反映されるのではなく「5年ルール」「125%ルール」(※)が設けられていることが多いです。
- ※「5年ルール」「125%ルール」は、元利均等返済のみ適用となります
5年ルールとは、見直された金利をもとに返済額を見直すのは5年後になることで、さらに見直し後の返済額が見直し前の返済額の125%を超えてはならないとされています。これが125%ルールです。ただし近年のネット銀行のなかには「5年ルール」「125%ルール」を設けていないところもあるため、申込時には商品概要説明書をよく確認するようにしましょう。
変動金利は、金利が低い点がメリットですが金利上昇局面には返済額が上がってしまうというデメリットがあります。もちろん大きく金利が上昇したとしても「125%ルール」が適用されるため、返済額が大幅に増えることはありません。しかし返済額に占める利息の割合が元本を上回る可能性もあります。この上回った部分のことを「未払利息」といい、最終返済時にまとめて支払うことが一般的です。
変動金利(年0.319%)
- ※最長で35年間金利が変わらない前提で計算
| 借入期間 | 毎月の返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
|
25年 |
13万8,738円 |
4,162万1,360円 |
|
30年 |
11万6,527円 |
4,194万9,646円 |
|
35年 |
10万666円 |
4,227万9,628円 |
固定期間選択型
固定期間選択型とは、2年・3年・5年・10年などあらかじめ決められた期間について固定金利が適用されます。特約期間終了後は変動金利と固定金利を選択できる場合が一般的です。ただし特約期間満了後、金利の優遇幅が縮小されてしまう場合がある点には注意が必要です。一定期間の返済額が固定されるため、住宅購入後に子どもの教育費などの支出が予定されているような人に向いています。
利率は、変動金利と全期間固定金利の中間に位置し、固定期間については金融機関によって選べる期間が異なるため、事前に確認しておきましょう。
固定金利選択型(当初10年:年1.325%、固定期間終了後:年1.6%)
| 借入期間 | 毎月の返済額 (固定期間) |
毎月の返済額 (固定期間終了後) |
総返済額 |
|---|---|---|---|
|
25年 |
15万6,706円 |
15万9,866円 |
4,758万531円 |
|
30年 |
13万4,714円 |
13万8,296円 |
4,935万6,638円 |
|
35年 |
11万9,073円 |
12万2,990円 |
5,118万5,721円 |
全期間固定金利
全期間固定金利は、住宅ローンの契約時から完済時まで適用される利率が変わらない金利タイプです。そのため将来にわたって返済額を固定させておきたい人に向いています。ただし利率は、3つの金利タイプのなかで高い金利水準となっているのが一般的です。
そのため金利負担をできるだけ少なくするためにも、余裕があるときには繰上返済を活用するなどして返済期間の短縮を心がけましょう。
全期間固定金利(年1.9%)
| 借入期間 | 毎月の返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
|
25年 |
16万7,601円 |
5,028万144円 |
|
30年 |
14万5,855円 |
5,250万7,790円 |
|
35年 |
13万461円 |
5,479万3,602円 |
住宅ローン控除の適用で負担を抑える
住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築すると、要件を満たすことで住宅ローン控除の適用が受けられます。
住宅ローン控除は、最大13年間、毎年の住宅ローン残高の0.7%を所得税や住民税から控除できる制度です。
所得控除ではなく税額控除で、年収800万円ともなれば課税される所得税額も大きくなるため、住宅ローン控除が適用されることで節税につながります。住宅ローン控除が適用されるための主な要件は、以下の通りです(2023年11月時点)。
- 購入する住宅はご自身が居住する住宅である
- 利用している住宅ローンの返済期間が10年以上ある
- 床面積が50平方メートル以上あり、居住部分の割合が2分の1以上ある
- 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
これらの要件を満たせば、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税額から差引かれます。適用される期間は最長13年ですが、給与所得者の場合、最初の1年目は確定申告を行わなければなりません。また購入物件や入居する時期によって、借入金額の上限が定められている点にも注意しておきましょう。高性能の住宅は、借入金額の上限が比較的高めに設定されているのが特徴です。
ただし、2024年から税制改正などに伴い、一部内容が次のように変更されています。
①省エネ基準を満たさない新築・買取再販住宅は控除を受けられない
②子育て世帯・若者夫婦世帯に対する控除が手厚くなり、19歳未満の子どもがいる・夫婦のいずれかが40歳未満、いずれかを満たす世帯は借入限度額が高く設定される
③新築住宅は床面積要件を40㎡以上に緩和する措置期間を延長する(ただし、合計所得1,000万円以下の人が借入れる場合に適用される)
また、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、住宅ローン控除を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

- ※表の右、オレンジ色の網掛けは借入限度額
年収やライフプランにあわせて住宅ローンを設計しよう
年収800万円の人が組める住宅ローンの金額は、4,000万~5,600万円程度です。ただし購入資金全額を借入れるのではなく頭金を用意するなどで毎月の返済額を抑えられます。また、住宅ローンを組むときには金利タイプを選ぶ必要があります。借入期間により異なりますが、金利タイプにより総返済額が大きく違ってきます。事前にシミュレーションし、無理のない返済額に収まるような金利タイプや借入期間を設定することが大切です。
本文内で説明した返済負担率を考えながら無理のない返済額に落ち着くように借入金額や借入期間、金利タイプを選ぶようにしましょう。