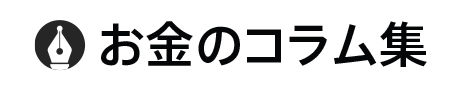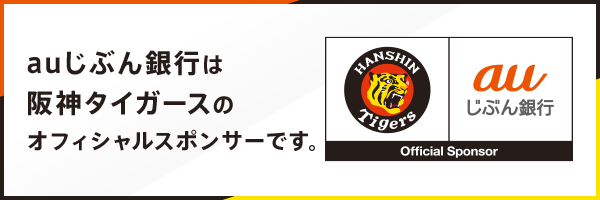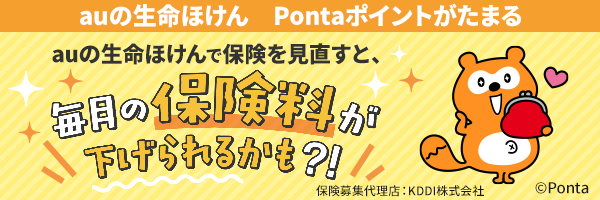2022/12/30
住宅ローンの「諸費用」の項目別の目安とは?節約方法も詳しく解説
監修者:新井 智美
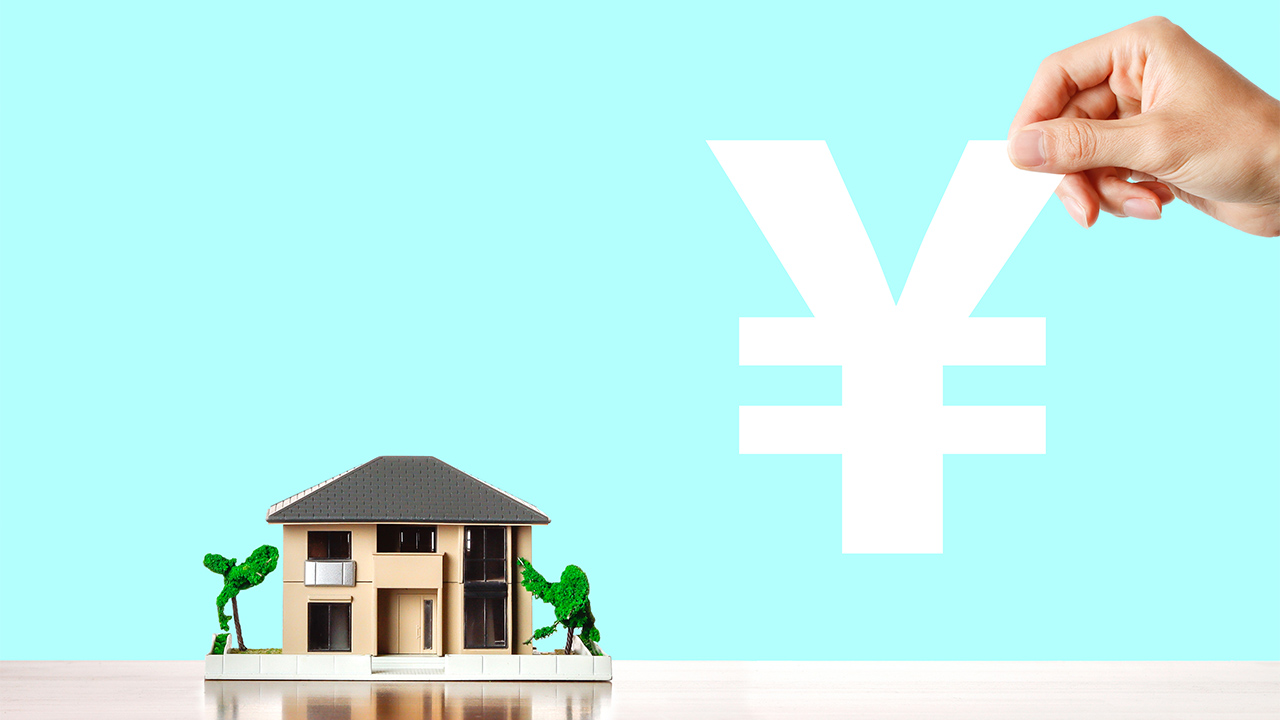
住宅ローンを組む場合、最初に金融機関に対して「諸費用」をまとめて支払う必要があります。貯金額に不安がある方は、「諸費用がどのくらいかかるのか」「自分に支払えるか」と気になっているかもしれません。
本記事では、住宅ローンの借入れを検討している方に向けて、諸費用の目安を項目別に紹介します。諸費用を低減する方法も詳しく解説するので、参考にしてください。
住宅ローンの諸費用の目安
住宅ローンを契約する際、金融機関に対して支払う諸費用は、分割ではなく、一括で支払わなければなりません。住宅ローンの諸費用の目安は2~6%です。
例えば、5,000万円の新築一戸建てを購入し、6%の諸費用がかかるとすれば、300万円を用意しなければなりません。大きな金額なので、あらかじめどう捻出するか考えておきましょう(「貯金を取り崩す」「株式や投資信託を売却する」「親に援助してもらう」など)。
なお、あくまでも目安であり、金融機関や住宅ローン商品によっては上記と異なる可能性がある点にご注意ください。
住宅ローンの諸費用①事務手数料
事務手数料とは、住宅ローンの借入れを行う金融機関に、契約事務手続きの対価として支払う手数料です。主に、以下に示す2種類のタイプがあります。
- 定額型:借入金額にかかわらず「一律数万円程度」といった、固定額になっているタイプ
- 定率型:「借入金額の数%程度」といった、借入金額によって変動するタイプ
住宅ローンの諸費用②印紙税
印紙税とは、住宅ローンの契約書に貼りつける印紙の代金です。住宅ローンの借入れは「金銭消費貸借契約」となり、下表に示す金額を納税しなければなりません。
| 契約金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 10万円 |
- ※2022年12月1日現在
なお、電子契約の場合は、印紙税が不要です。
住宅ローンの諸費用③保証料
保証料とは、契約者がローンの返済を行えなくなった場合に備えて、保証を引き受けてもらうために保証会社に支払う費用です。万が一、契約者がローンの返済を続けられなくなった場合、保証会社が金融機関に代位弁済を行います。
なお、代位弁済後、契約者は保証会社へ返済することとなるため、契約者の住宅ローン支払い義務が無くなるわけではありません。
「契約時の一括支払い」と「毎月のローン返済額への上乗せ」の2種類の支払方法があり、金融機関によって異なると覚えておきましょう。
借入金額と返済期間に応じて決まり、一括前払いの場合は借入金額の2%程度(例えば、1,000万円の住宅ローンなら、20万円程度)、毎月のローン返済額への上乗せの場合は金利が年0.2%~年0.4%程度が目安となります。
保証会社が不要な金融機関の場合、保証料はかかりません。
住宅ローンの諸費用④登記関連費用
住宅ローンを契約する際には、「抵当権」の設定が必要になります。抵当権とは、住宅ローンの契約者が返済を続けられなくなった場合に、金融機関や保証会社が不動産を差し押さえる権利です。
なお、抵当権設定時に「登録免許税」を納付しなければなりません。登録免許税の税額は「住宅ローン借入金額の0.1%」とされている(2026年3月31日までの軽減措置)と覚えておきましょう。また、一般的に、司法書士への報酬は「6~10万円前後」が目安となります。
住宅ローンの諸費用⑤火災、地震保険料
火災保険への加入が、住宅ローン契約の条件になっている場合があります。火災保険の保険料は、保険期間10年であれば、補償内容によって「数万円~数十万円程度」が相場です。
なお、地震による損害は火災保険の対象外です。地震保険は単独で加入できないため、火災保険に上乗せで加入する形式になることを覚えておきましょう。
住宅ローンの諸費用⑥団体信用生命保険料
「団体信用生命保険」とは、契約者が亡くなったり、高度障害の状態になったりした場合に、保険金によって住宅ローンの残高を完済する保険です。多くの民間金融機関では、住宅ローンの借入れの際に、団体信用生命保険への加入は必須です。
金融機関によってさまざまですが、団体信用生命保険料がゼロで、金利の上乗せもないケースも存在します。
なお、「死亡」や「高度障害」だけではなく、「がん(所定の悪性新生物)と診断確定された場合」「10種類の生活習慣病で入院が継続180日以上となった場合」」などに住宅ローンが完済される特約を付加している場合は、年0.1〜0.3%程度の金利の上乗せが行われるのが一般的です。
諸費用を毎月の返済額に組み込み可能な場合もある
先述してきたように、諸費用には「一括での支払いも、毎月の返済額への組み込み(上乗せ)も可能なもの」と「一括で支払う以外の選択肢がないもの」が存在します。
一括で支払う必要がある項目だけでも高額になるため、「今すぐ用意するのは難しい」と感じる方もいるかもしれません。
なお、金融機関によっては、物件の購入費用に、諸費用(月々の支払いに上乗せができないタイプの諸費用を含む)を上乗せした金額で住宅ローンを組むことも可能です。初期費用を抑えたい方は、諸費用も含めた金額の住宅ローンを組める金融機関を利用してはいかがでしょうか。
住宅ローン諸費用を節約する方法
以下は、住宅ローンの諸費用を節約する方法です。
- 頭金(自己資金)を多めに用意する
- インターネット上で電子契約を行う
- 火災保険の補償内容を精査する
頭金(自己資金)を多めに用意する
頭金(自己資金)を多めに用意すれば、住宅ローンの借入金額を抑えられます。
住宅ローンの借入金額が小さくなると、連動して「事務手数料(定率型の場合)」や「保証料」「登記関連費用(登録免許税)」なども低減されると認識しておきましょう。
しかし、無理に多額の頭金(自己資金)を捻出しようとして、「万が一の事態(急な病気、ケガ、自然災害など)に備えるための資金」に手をつけるのは避けたいところです。手元資金が枯渇しないように、バランスを考えてください。
インターネット上で電子契約を行う
昨今、インターネット上で住宅ローンの電子契約が可能な金融機関が増加しています。
先述したように、電子契約の場合、印紙税が不要です。「少しでも諸費用を抑えたい」と考えている方は、電子契約を検討してはいかがでしょうか。
火災保険の補償内容を精査する
火災保険の補償内容を精査し、必要な補償だけ残して、不要なものを外すと保険料を低減できます。しかし火災保険は備えなので、必要以上に補償を外してしまうと万が一の際に困ってしまう可能性もありますので注意しましょう。
なお、「金融機関から案内された火災保険にしなければならない」わけではなく、ご自分で選択も可能です。同じような補償でも、火災保険の種類によっては保険料が割安なケースもあるので、内容を比較、検討しましょう。
住宅購入後にかかるコストも確認すること
住宅購入後には、さまざまなコストがかかります。以下は具体例です。
- 引越し費用
- 不動産取得税
- 修繕積立基金
住宅に入居する際は「引越し費用」が必要になります。近所に住んでいる、友人や知人、家族に手伝ってもらえる場合は、低額あるいはゼロに抑えられるかもしれません。
「不動産取得税」とは、土地や建物を取得した際に、都道府県に対して納める税金です。税額は、原則として「固定資産税評価額の4%」ですが、2024年3月31日までに取得した土地や住宅は、3%に税率が軽減される特例があります。さらに、別の軽減措置も存在するので、詳細は税務署や不動産業者、金融機関に問い合わせてください。
「修繕積立一時金」とは、新築の分譲マンションを購入した際に発生する費用です。「修繕積立準備金」や「修繕積立基金」と呼称される場合もあり、金額はマンションの規模によって異なりますが、一般的に数十万円程度です。
また、分譲マンションでは、「修繕積立一時金」とは別に、入居後に毎月「修繕積立金」をマンション管理組合に対して支払わなければなりません。
住宅ローンを組む際には、諸費用の金額もチェックしよう
本記事で紹介したように、住宅ローンの契約には、さまざまな「諸費用」が発生します。トータルで数百万円になる場合も多いので、「頭金(自己資金)を多めに用意する」「インターネット上で電子契約を行う」「火災保険の補償内容を精査する」方法で、少しでも諸費用の低減に努めましょう。
なお、住宅購入後には、「引越し費用」「不動産取得税」「修繕積立基金」などのコストもかかります。住宅ローンの借入れを行う際には、トータルでどのくらいの資金が必要になるのか把握しましょう。
諸費用で不明な点がある場合は、一人で悩まず、金融機関の窓口やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してください。