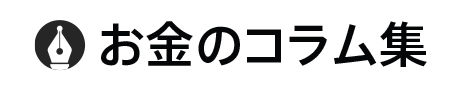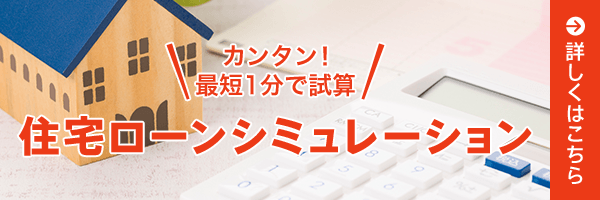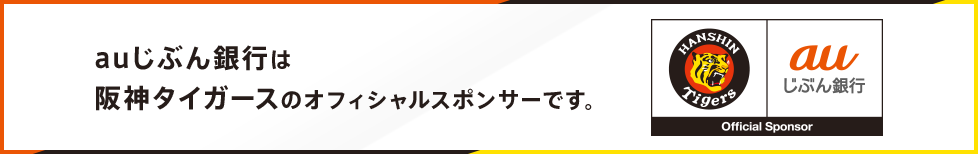2022/10/18
住宅ローンの借入可能額はどう決まる?目安を知る方法や注意点を解説
監修者:竹下 昌成

住宅ローンの借入可能額がわかれば、マイホームの予算も立てやすいでしょう。
しかし、借入可能額は金融機関により決定されるため、必ずしもご自身が希望する金額になるとは限りません。
では、住宅ローンの借入可能額は何を基準に、どのようにして決まるでしょうか。
本記事では、住宅ローンの借入可能額の決まり方や、ご自身で目安を知る方法などを解説します。
住宅ローンの借入可能額はどう決まる?
金融機関の審査基準は非開示なので、住宅ローンの借入可能額を決定するための要素を明確に示すことは出来ません。
しかし、住宅ローンの申込み時に必要な情報から、借入可能額を決める要素の予測は可能です。
住宅ローンの借入可能額を決める際、金融機関が考慮すると考えられる要素を確認していきましょう。
現在の年収
住宅ローンの審査に欠かせないのが、給与所得者であれば源泉徴収票と住民税決定通知書、自営業者であれば確定申告書のように、現在の年収を証明する書類です。つまり、年収は借入可能額を決定する重要な要素の1つであると考えられます。
実際、借入限度額は年収(総支給額)と大きく関係します。金融機関は住宅ローンで多額の融資を行うため、申込者の返済能力を重要視します。
年収に対する年間のローン返済額の割合(返済負担率または返済比率)が、一定割合を超えないように、借入限度額を判断しています。
詳しくは後述しますが、年収から借入可能額を逆算するシミュレーションもあります。気になる方は一度計算してみるのも良いでしょう。
購入物件の価格
住宅ローンの融資対象となるマイホームの購入価格あるいは建築費用によっても、借入限度額は変動するとされます。
第一に、対象物件は住宅ローンの担保となるため、価格を含む総合的な評価が借入限度額に影響を及ぼします。
そして第二に、さきほどの返済負担率のように、金融機関の多くが物件購入にかかる費用総額(物件購入価格+諸費用)に対する借入金の割合を指標としています。 一般的に、例えば必要資金総額が5,000万円(物件価格4,800万円+諸費用200万円)の場合、自己資金1,000万円を用意し4,000万円の借入れを希望するのと、自己資金を用意せず5,000万円フルで借入れを希望するのでは、後者の方が審査は厳しくなるでしょう。
他ローンの利用状況
マイカーローンを返済中である、クレジットカードのリボ払いをしているなど、他ローンの利用状況も住宅ローンの借入限度額を左右します。
先述の返済負担率は、住宅ローン以外のローンの返済金額も考慮して計算されるため、他ローンで残債がある場合、返済負担率が高くなりすぎないように、住宅ローンの借入限度額が低くなる可能性があります。
申込時の年齢
通常、住宅ローンの申込条件には、申込時の年齢が提示されています。
例えば、auじぶん銀行では「満18歳以上満65歳未満で、最終ご返済時が満80歳の誕生日まで」と明記しています。申込みの前提となっているため、該当しない方は原則として住宅ローンを利用できません。
年齢条件に従えば、契約時の年齢が一定年齢を超えるとローン完済までの期間は短くなり、毎月の返済額の負担が重くなるため、借入時の年齢が高いと借入限度額が低くなる可能性があります。
住宅ローンのシミュレーションで借入可能額を確認しよう
住宅ローンの借入限度額は、金融機関が決定するため、ご自身の希望する金額に決まるかどうかはわかりません。
しかし、マイホームの候補を絞るためにも、おおまかな借入限度額の目安を知っておくと便利です。
銀行の公式サイトなどが提供するシミュレーションツールを利用すれば、年収や毎月の希望返済額など、今わかっている情報を入力するだけで、誰でも簡単に住宅ローンの借入限度額をシミュレーションできます。
今回は、auじぶん銀行が公式サイトで提供しているシミュレーションツールを使って、具体的な金額をもとに、住宅ローンの借入可能額について調べてみましょう。
毎月の返済額を調べる
通常、住宅ローンは、毎月決まった金額を返済します。完済までは毎月の固定費となるため、生活に負担のかからない程度にとどめておきましょう。
借入可能額を知る前に、まずは、希望する借入金額で住宅ローンを組んだ場合、毎月の返済額はいくらになるかを把握しておきましょう。
シミュレーションの条件として、「借入金額3,000万円、借入期間35年、元利均等返済、全期間引下げプラン・変動金利年0.389%(2022年10月現在)、ボーナス返済なし」で試算します。
| 毎月の返済額 |
76,412円 |
|
|---|---|---|
| 総返済額(借入金額+利息) |
32,093,229円 |
|
| 諸費用 |
事務手数料 |
660,000円 |
|
登記関連費用 |
205,000円 |
|
| 総費用(総返済額+諸費用) |
32,958,229円 |
|
- ※本シミュレーションは2022年10月時点のもので、実際の事例とは異なる場合がございます。
- ※所有権保存・所有権移転・既存担保権抹消などの一部登記費用、火災保険の保険料などの諸費用は含まれておりません。
毎月の返済額が適正かどうかを判断するのに役立つのが、現在払っている家賃+毎月の住宅購入用の貯蓄です。同水準の金額に抑えておけば、無理のない返済が可能でしょう。
しかし、マイホームの購入後は、固定資産税・都市計画税・修繕費などの維持管理費を別途用意しなくてはなりません。現在の家賃よりやや控えめにしておくと安心です。
また、マンションの場合は管理費、修繕積立費、駐車場代などがかかります。それらが将来的に値上げになった場合も考えておきましょう。また、今回の試算は変動金利です。返済額が上昇した場合の試算も組み入れておきましょう。
現在の年収から借入可能額を調べる
今度は現在の年収から、住宅ローンの借入可能額を計算します。年収500万円、借入期間35年、元利均等返済、全期間引下げプラン・変動金利年0.389%(2022年10月現在)、他に返済中の借入れはないものとしてシミュレーションします。
| 借入可能額 |
39,200,000円 |
|
|---|---|---|
| 毎月の返済額 |
99,846円 |
|
| 総返済額(借入金額+利息) |
41,935,201円 |
|
| 諸費用 |
事務手数料 |
862,400円 |
|
登記関連費用 |
245,000円 |
|
| 総費用(総返済額+諸費用) |
43,042,601円 |
|
- ※本シミュレーションは2022年10月時点のもので、実際の事例とは異なる場合がございます。
- ※所有権保存・所有権移転・既存担保権抹消などの一部登記費用、火災保険の保険料などの諸費用は含まれておりません。
年収500万円に対して、借入可能額は約3,900万円との結果をみて、たくさん借りられると感じた方もいるかもしれません。
しかし、毎月の返済額が10万円近くあり、毎月の返済額が負担になる場合もありえます。借りられるだけ借りることがプラスになるとは限りません。
住宅ローンの審査はサラリーマンの場合は年収、つまり総支給額で審査します。いわゆる手取りで考えると予想より生活の圧迫感を感じることもあるでしょう。「借りられる額と返せる額は違う」ということです。
フラット35を提供する住宅金融支援機構の「2021年度 フラット35利用者」によると、実際に住宅ローンを利用した方の借入額は、注文住宅の場合は年収の6.8倍、中古マンションの場合は年収の5.8倍が平均値とのことです。
つまり、年収500万円であれば、注文住宅なら3,400万円、中古マンションなら2,900万円がひとつの目安といえるかもしれません。
毎月の返済額から借入可能額を調べる
最後に、毎月の希望返済額から、住宅ローンの借入可能額を計算します。
毎月希望返済額を8万円・ボーナス分の希望返済額0円、借入期間35年、元利均等返済、全期間引下げプラン・変動金利年0.389%(2022年10月現在)として、シミュレーションを行います。
| 借入可能額 |
31,400,000円 |
|
|---|---|---|
| 年間返済額 |
959,736円 |
|
| 総返済額(借入金額+利息) |
33,590,927円 |
|
| 諸費用 |
事務手数料 |
690,800円 |
|
登記関連費用 |
245,000円 |
|
| 総費用(総返済額+諸費用) |
34,526,727円 |
|
- ※本シミュレーションは2022年10月時点のもので、実際の事例とは異なる場合がございます。
- ※所有権保存・所有権移転・既存担保権抹消などの一部登記費用、火災保険の保険料などの諸費用は含まれておりません。
借入可能額は、今までのシミュレーションのなかでは、抑えられた金額となりました。5,000万円以上の住宅購入を検討しているなら、3,140万円の借入額は心許ないかもしれません。そうした場合は、毎月の返済額を増やす必要があるでしょう。
しかし、住宅ローン返済は数十年続くことがほとんどです。転職や失業など、予測できないライフプランの変化も起こりえます。
また、近年は夫婦共働きが増えてきました。特に大都市部では夫婦で合算した年収の上限まで住宅ローンを組むケースも散見されます。妊娠や出産、その後の働き方などもよく考えましょう。
住宅ローンの返済が重い負担とならないよう、多少の収入の変化にも対応できる、無理のない借入額とすることが重要です。
住宅ローンの借入可能額に関する注意点
シミュレーションで判明する借入可能額の予測も、申込み後に金融機関が提示する融資金額も、対応可能な借入金額というだけであって、個々の生活にあわせて無理なく返済できる金額というわけではありません。
住宅ローンでは、まとまった金額のお金を借りて、長い期間をかけて返済を続けることになります。生活に負担とならない返済プランが大切です。
さらに、住宅ローンの借入可能額については、次の3つにご注意ください。
諸費用や住宅の維持費用に注意する
マイホームの購入には、住宅自体の費用だけではなく、住宅ローンにかかる各種手数料、税金などさまざまなコストがかかります。一時金として支払うには大きな金額なので、しっかりと準備しておかなければなりません。
また、マイホームでの生活がスタートすると、早速、毎月の住宅ローン返済も始まります。
さらに忘れてはならないのが、住宅の維持費です。
壁や屋根の修繕、水回りなど故障した設備の修理といった不意の出費に対応できるよう、毎月一定の金額を維持費として積み立てておくと安心です。
マンションの場合は、専用居室部分をご自身で修繕するのはもちろん、修繕積立費や管理費など管理組合へ毎月支払いが発生するため、返済に加え、毎月支払う金額がいくらになるのかを把握しておきましょう。
ボーナス併用支払いはリスクを考慮する
住宅ローンの借入可能額をシミュレーションするときには、ボーナス払いを選択できます。ボーナス払いを併用すれば、毎月の返済額を減らせて、心理的な負担も減るでしょう。
しかし、ボーナスを見込んだ住宅ローンの返済にはリスクが伴います。会社の業績悪化や転職などによってボーナスがなくなるのは、今の時代、珍しい出来事ではありません。
受け取れ続けるかどうかわからないボーナスは、あくまで臨時収入と考え、住宅ローンは毎月の給料からの返済を基本とする計画がおすすめです。もしボーナスによって生活資金に余裕が出れば、繰上げ返済に活用するのも一手です。
金利タイプの違いを意識する
住宅ローンの金利タイプには、変動金利、全期間固定金利、期間選択型固定金利があります。同じ銀行で同じ借入額の住宅ローンを組んだとしても、金利タイプによって、総支払額が大きく異なる可能性があります。
変動金利は、半年ごとに金利の見直しが行われます。低金利が続く今、返済額における元金の割合が高く、利息の支払いの少ない効率の良い返済が可能です。
しかし、今後金利が上昇すると、利息の支払いが増え、元金をなかなか減らせないリスクもあります。
全期間固定金利は、市場金利にかかわらず、契約時の金利が返済中ずっと続きます。毎月安定した返済額のため、ライフプランを立てやすいといえます。しかし、変動金利よりも金利が高く、低金利時代では利息の支払いが多くなります。
期間選択型固定金利は、契約当初の2年、5年、10年など、一定期間のみ固定金利となり、期間終了後に金利タイプをあらためて選び直します。数年後の金利動向を読むのは難しいですが、当初金利が格安に設定されている住宅ローンもあります。
住宅ローンの借入可能額は生活の負担にならない金額にしよう
住宅ローンの借入可能額は、銀行に申込み手続きをする前に、ご自身でシミュレーションして把握しましょう。年収や毎月の返済希望額、他のローンの利用状況などから、簡単に目安を知ることができます。
毎月の生活を圧迫する、年収に占める割合が高すぎるなど、不安を感じるようなら、たとえ借入れが可能であっても、余裕のある借入額になるよう見直しましょう。
また、マイホームを購入すると、住宅の購入以外にも、各種手数料や税金などが発生します。そうしたコストも考慮しながら、余裕をもった資金計画を立てると良いでしょう。