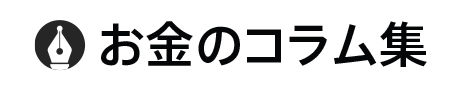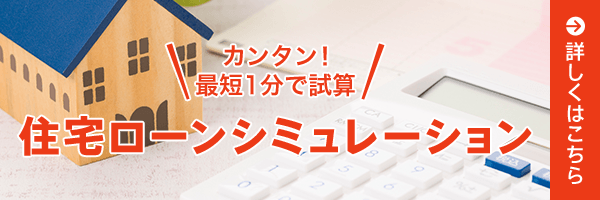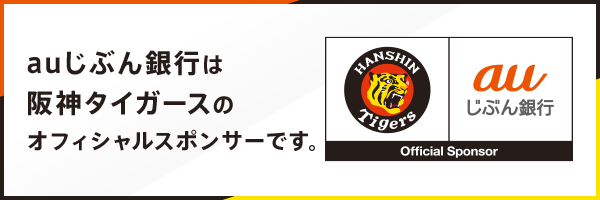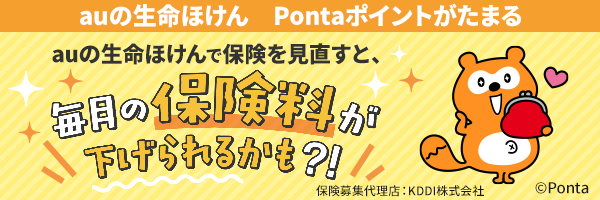住宅購入の頭金の目安は?ローンの組み方・金額について解説
執筆者:佐藤名ゝ美(ファイナンシャルコーチ)
2022年2月14日

住宅取得資金計画は、検討すべきポイントがいくつかあります。「住宅ローンをどこから、いくら借りるか」「返済期間をどのように設定するか」「ボーナス払いをいくらにするか」、そして「頭金をどうするか」もその一つです。ここでは頭金について、どのように考えればよいか整理していきましょう。
頭金の目安は?
住宅の頭金の目安として「物件価格の1~2割」といった表現を見かけたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。例えば4,000~5,000万円あたりの価格帯で物件を購入する場合、400~1,000万円程の頭金を用意する必要があるということになります。資金が準備できていて、問題なく支出できるというケースもあるかもしれません。一方で、ハードルが高いと感じる方も多いかもしれません。
頭金を十分に用意できれば、住宅ローンの借入額を抑えられ、月々の返済がより楽になります。住宅ローン商品の中には、頭金をより多く入れることよって金利が低く設定されるものもあります。一方、手持ち資金を総動員して住宅の頭金に充ててしまうと、不測の事態に対応できなくなってしまうリスクを抱えることになります。加えて、子どもの進学や車の買い替えといった他の資金需要にも多大なる影響を与えることも避けられません。
頭金の金額は、一般的に住宅購入価格の1~2割と言われていますが、住宅資金計画全体と家計の収支や資産状況全体のバランスを取りながら、自分たちに合った組み立てを考える必要があります。
頭金は「なし」でもローンは組める?
頭金なしでも住宅ローンは組むことが可能です。しかし、誰でも確実に組めるわけではありません。金融機関が住宅ローンの申込みを受けると、その人の収入や他のローンの状況、信用情報や購入予定物件などを勘案し、いくらまで融資できるか判断します。審査を経て、購入予定物件の価格まで満額の融資が可能と判断されれば、頭金なしでも融資を受けられます。
購入予定物件の価格まで融資がおりない場合は、差額を頭金として入金しなければなりません。または、その物件は諦めて予算額を縮小するかの二者択一になるでしょう。
頭金の金額の決め方は?
頭金の金額の決め方には、以下の3つの要素があります。これらの要素を状況により組み合わせて検討してください。
1.物件価格に対して融資額が不足する場合
前述の通り、物件価格に対して融資額が不足する場合は、必然的に頭金を入れて差額を埋め合わせる必要があります。
2.住宅ローンの返済負担から割り出す
月々無理なく返済でき、適切な時期に完済できる金額から、住宅ローンの借入額を決定します。決めた住宅ローンの借入額と物件価格との差額が、頭金として用意したい金額になります。
具体的に計算してみましょう。以下は「住宅ローン100万円あたりの返済額目安」を表にまとめたものです。
【住宅ローン100万円あたりの返済額目安表(元利均等返済の場合)】(単位:円)
| 返済期間 | 返済方法 | 適用金利 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年0.5% | 年0.7% | 年1.0% | 年1.2% | ||
| 25年 | 月々 | 3,547 | 3,635 | 3,769 | 3,860 |
| ボーナス | 21,301 | 21,836 | 22,654 | 23,210 | |
| 30年 | 月々 | 2,992 | 3,081 | 3,217 | 3,309 |
| ボーナス | 17,969 | 18,507 | 19,333 | 19,896 | |
| 35年 | 月々 | 2,596 | 2,686 | 2,823 | 2,917 |
| ボーナス | 15,590 | 16,132 | 16,967 | 17,538 | |
上記を用いて、例えば月々10万円、ボーナス時に10万円の返済が可能な家庭が、金利年0.5%、35年返済でローンを組む場合
- ①月々返済にて対応する借入額を計算
100,000円÷2,596円=38.5
目安表の数字は、100万円あたりの返済額なので
38.5×100万円=3,850万円 - ②ボーナス返済にて対応する借入額を計算
100,000円÷15,590円=6.4
同じく目安表の数字は、100万円あたりの返済額なので
6.4×100万円=640万円
①②を合計すると、月々返済額からみた住宅ローン借入額は
3,850万円+640万円=4,490万円
となります。
ここからは、購入予定物件との差額を求めましょう。物件価格が5,000万円であれば510万円が、物件価格が4,600万円であれば110万円が、必要な頭金の金額ということになります。
なお、住宅購入時および住宅ローン借入時は各種諸費用がかかります。借入金額は別途発生する諸費用も考慮して検討するようにしましょう。
3.住宅ローン減税(住宅ローン控除)を考慮する
一定の住宅ローンの借入金残高に応じ、住宅取得から10年(契約時期によっては13年)にわたり、所得税および住民税において税額控除を受けられるのが、いわゆる「住宅ローン減税(控除)」です。
同制度によって減税される金額は、年末の住宅ローン残高の1%です。なお、住宅ローン残高には上限が設けられており、長期優良住宅で5,000万円、一般住宅で4,000万円となります。(※2021年度税制)
住宅ローン減税(控除)の改正についても検討されているようですが、引き続き恩恵は受けられると考えられます。
よって、住宅ローン減税(控除)が適用される期間においては、控除額に対応する残高までは住宅ローンを借りておくのも、家計にとって有効な作戦と考えられるのではないでしょうか。住宅ローン減税(控除)の上限額に対応する金額までは住宅ローンを借りておき、それを超える金額については頭金を入れるというのも一つの考え方です。
手元に多くの資金を温存しておく方が、ライフプラン上の選択肢が広がる可能性は高まります。また、住宅ローンには基本的に団体信用生命保険が付帯されます。団体信用生命保険のことを考慮すると、万一の場合を考えても、手元資金を薄めてまで借入金額を減らすことに優位性は見出しにくいといえるでしょう。
一般的な目安に惑わされず柔軟に検討を
一般的に、頭金の「目安」と呼ばれる数字は、不特定多数に向けてわかりやすくしたもので最大公約数でしかありません。大切なのは「どのようにして希望の状態を組み立てていくか」です。住宅の頭金は、住宅ローンの借入額と無理のない返済額、手元資金の残高と他のライフプラン、税制優遇などを踏まえ、全体的なバランスを見ながらご家庭にあった金額を柔軟に検討してください。