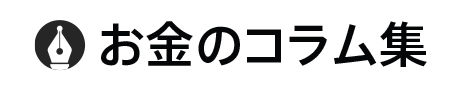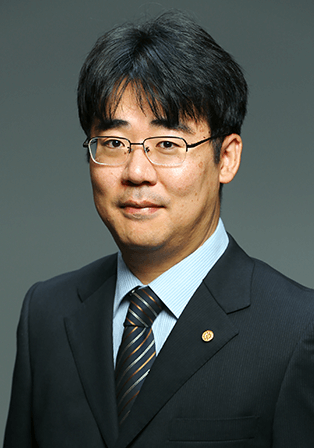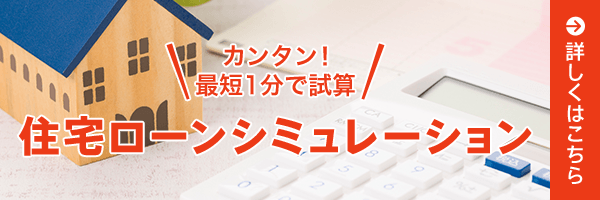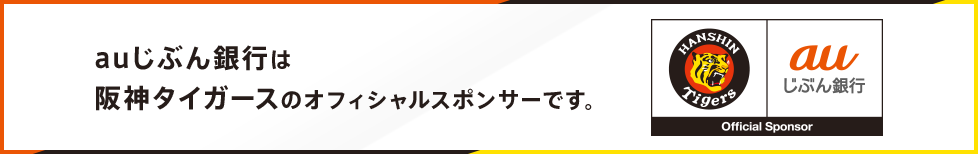知っておきたい!住宅ローン減税(住宅ローン控除)制度の変更点や注意点をFPが解説
執筆者:上田 健介(ファイナンシャルプランナー)
2020年8月25日
(2021年7月5日 令和3年度税制改正の内容を追加)(2022年7月14日 内容一部更新)

2019年10月に消費税の税率が8%から10%へ引き上げられました。消費税の引き上げによる影響を考慮して、「住宅ローン減税(控除)」の制度も変更されています。この制度変更は、住宅を取得したいと考えている人の金利負担を軽減し、住宅業界の販売落ち込みを緩和させようとするものです。今回は、住宅ローン減税(控除)制度の変更点と注意点について解説します。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)とは
住宅ローン減税は、「住宅ローン控除」と表記されることがありますが、正式名称を「住宅借入金等特別控除」と言います。個人が住宅ローンを利用して、住宅を取得(新築、新築住宅の購入、中古住宅の購入、住宅の増改築など)したときに、一定の割合にあたる金額が所得税から控除されます。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)制度の変更点(消費増税)
消費税率10%の適用を受ける住宅を取得した場合、控除を受けられる期間が10年から13年に延長されます。13年の控除が受けられるのは、契約期限および入居期限の両方を満たしている場合です。契約期限・入居期限はそれぞれ以下のとおりです。
- 契約期限
注文住宅を新築する場合
・・・2021年9月30日
分譲住宅・既存住宅(中古住宅)を取得する場合、増改築等をする場合
・・・2021年11月30日 - 入居期限
・・・2022年12月31日
取得する住宅の種類により、控除額の上限が異なります。住宅の種類ごとの上限を確認しておきましょう。
■一般住宅
<1~10年目の控除額>
住宅借入金等年末残高(上限4,000万円)×1%=上限40万円/年
<11~13年目の控除額>
- 住宅借入金等年末残高(上限4,000万円)×1%=上限40万円/年
- 建物購入価格(上限4,000万円)×2%÷3=上限26.66万円/年
上記のうち、いずれか少ない方
■認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)
<1~10年目の控除額>
住宅借入金等年末残高(上限5,000万円)×1%=上限50万円/年
<11~13年目の控除額>
- 住宅借入金等年末残高(上限5,000万円)×1%=上限50万円/年
- 建物購入価格(上限5,000万円)×2%÷3=上限33.33万円/年
上記のうち、いずれか少ない方
住宅ローン減税(住宅ローン控除)と一緒に知っておきたい制度(補助金)
住宅を取得したい人の負担を軽減する効果がある制度は、住宅ローン減税(控除)だけではありません。ここでは、住宅ローン減税(控除)と一緒に知っておきたい制度をピックアップします。
■すまい給付金
住宅ローン減税(控除)は一定の割合にあたる金額が所得税から控除されますが、「ある程度の所得がある」ということが前提になります。控除すべき(マイナスすることができる)所得が多くなければ、その恩恵を受けづらくなります。そこで、すまい給付金でお金を給付することで、より多くの人が負担を軽減できるようにしています。消費税10%で住宅を取得したときの最大給付額は50万円です。
■住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例
平成27年1月1日~令和3年12月31日の間、「住宅を購入する目的で直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与を受けた」場合に贈与税が非課税となります。もっとも、常に贈与額全額が非課税になるわけではなく、住宅を購入した時期やその住宅の種類によって異なります。例えば、契約締結日が令和3年4月1日~令和3年12月31日における非課税限度額は1,000万円(省エネなどの条件を満たした住宅は1,500万円)となっています。
そして、この非課税の適用を受けるためにはいくつかの要件があります。
- ①贈与を受ける人
- 贈与を行う人の直系卑属(子、孫、ひ孫)であること。
- 20歳(贈与を受けた年の1月1日時点)以上であること。
- 合計所得金額(贈与を受けた年分)が2,000万円以下であること。
(新築等の住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)
- 贈与を受けた翌年3月15日までに自分の名義で住宅を取得し居住すること。
- ②住宅
- 家屋は日本国内にあること。
- 家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、その家屋の床面積の2分の1以上が贈与を受けた人の居住用であること。
- 中古住宅の場合は、築20年以内(耐火建築物は築25年以内)であること。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)制度を利用する際の注意点
ここでは、制度利用時の注意点をご紹介します。いくつかある注意点のうち、特に筆者がよく相談者から質問を受ける内容を挙げています。
①確定申告が必要
住宅ローン減税(控除)は、要件を満たしている住宅を取得することで自動的に適用を受けられるわけではありません。必ず最低1回は確定申告が必要です。特に、お勤めの会社による年末調整しか経験がない方は、早めに確定申告についての知識や情報を得ておきましょう。
②繰上げ返済との優先
住宅ローン減税(控除)と繰上げ返済のどちらを優先させようか悩むことがあります。どちらを優先させるか決める際は厳密に計算してみるべきです。しかし、一つの目安として、「利用している住宅ローンの金利に着目してみる方法」があります。住宅ローン減税(控除)は借入金残高の1%を控除するようになっているため、住宅ローンの金利が1%を超えるかどうかをチェックします。ただし、所得税などの納税額の影響も受けるため、あくまでも簡易的に判断する方法ではあります。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)制度の適用条件
住宅ローン減税(控除)は、すべての住宅で一律に受けられるものではありません。以下に代表的な条件をまとめました。実際に適用を受けようとする場合には、税務署の相談コーナーなどで事前に確認しておくと安心でしょう。
| 新築 |
|
|---|---|
| 中古 | ①~⑥に加えて
|
| 増改築等 | ①、③~⑥に加えて
|
| 土地 | 原則として土地を取得するためのローンは適用外 (ただし建物の新築にかかるローンがある場合には適用可) |
住宅ローン減税(住宅ローン控除)制度で戻ってくる金額
住宅ローン減税(控除)の変更点で控除額について触れましたが、これは控除できる最大の金額を示したものであり、常に全員が最大金額の控除を受けられるわけではありません。しかしながら、実際に自身の数字を当てはめようとすると複雑な計算が必要になります。
ここでは、国土交通省「すまい給付金」のウェブページに設けられているシミュレーションを利用してみます。すまい給付金のみならず住宅ローン減税の確認もでき、どの程度負担軽減効果があるのか一目瞭然です。もちろん、名前や住所などの個人情報を入力する必要はありません。筆者が架空の条件でシミュレーションした結果は、次の通りでした。
<条件>
取得時の適用消費税率…10%、所有権…一人で所有、住宅ローンの利用…有
年収…675万円、扶養家族…3人、住宅価格…建物2,000万円、土地2,000万円、
入居予定…令和3年12月、借入額…3,000万円、ボーナス払い…0万円、年利(固定)…2%、借入期間…30年、返済開始月…1月
<結果>
すまい給付金…300,000円
住宅ローン減税(控除)額…初年度292,600円、控除期間合計2,968,400円
住宅ローン減税(住宅ローン控除)制度を利用するための必要書類と手順
制度利用の手続きは、適用を受けようとする最初の年と2年目以降で異なります。最初の年は、確定申告を行う必要があります。確定申告書に必要事項を記載し、書類を添付して税務署(原則として住所を管轄している税務署)に提出します。一方、2年目以降は、必ずしも確定申告を行う必要はなく、年末調整で済ませることも可能です。主な必要書類は次の通りです。
<最初の年>
- 住民票(市区役所もしくは町村役場で入手)
- 確定申告書(国税庁ウェブサイトで入手)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から送付)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁ウェブサイトで入手)
- 登記事項証明書(法務局で入手)
- 契約書
- 源泉徴収票(給与所得者の場合に勤務先から支給)
<2年目以降>
- 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送付)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から送付)
住宅ローン減税(住宅ローン控除)にとらわれすぎない
これまでに解説してきた通り、住宅ローン減税(控除)は住宅ローンの残高によって控除される金額に差があります。このことから「なるべく住宅ローンで多くの金額を借り入れて、多くの控除を受けた方が良さそう」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
しかし、多くの金額を借り入れるということは、それだけ返済の負担も大きくなるということです。今は十分余裕があると思っていても、子供の人数や年齢によって家計の状況が変わっていくこともあるでしょう。月々の返済額がどのくらいになるのかシミュレーションを行い、無理のない金額か確認しておきましょう。
住宅ローン減税(控除)は、住宅ローンを利用する人にとって忘れてはいけない制度であることは間違いありませんが、日常生活(ライフプラン)を見据えることも大切です。