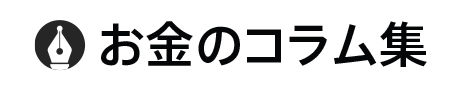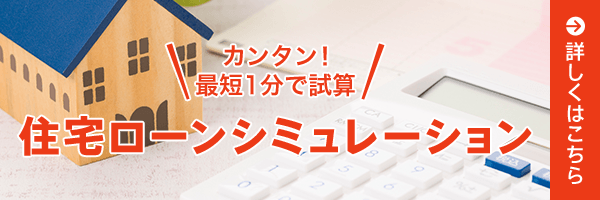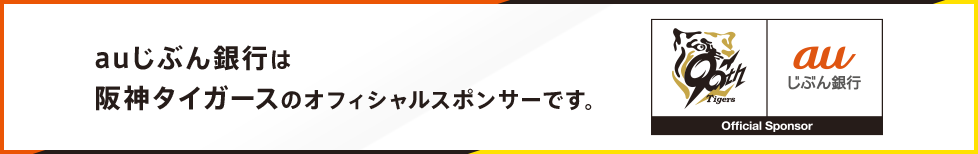2023/2/3
住宅ローンの金利タイプを変更するならいつ?タイミングや方法、注意点を解説
監修者:新井 智美

住宅ローンの金利タイプは、住宅ローン返済中でも変更することが可能な場合があります。
金融緩和政策の影響から長く低金利が続く日本ですが、住宅ローンは返済期間が長いため、将来の見通しは不透明です。金利の変動を意識して、よりよい金利タイプへ変更することも視野に入れましょう。
この記事では、住宅ローンの金利タイプを変更する最適なタイミングや具体的な方法などを解説します。
住宅ローンの金利タイプの種類
住宅ローンの金利タイプは、「変動金利」と「固定金利」の2種類があります。固定金利は契約時の金利が適用される期間に応じて、さらに「全期間型」と「期間選択型」に分かれます。
どの金利タイプを選択するかは、住宅ローンの契約時に契約者が決めることになります。それぞれに異なる特徴があり、とくに違いが出やすいのが金利です。
そこでまずは、住宅ローンの金利タイプについて、それぞれの種類ごとの違いを確認しておきましょう。
変動金利
変動金利は、住宅ローンの返済期間中、定期的に金利の見直しが行われるタイプです。金利情勢に影響を受けるため、低金利が続く今、多くの金融機関で固定金利よりも低い金利が設定されています。
金利の見直しは、通常、半年ごとに行われます。金利が上昇した場合、総返済額が当初の予定よりも多くなる可能性もあります。
また、金利が大きく上昇すると、支払い利息だけで月々の返済額を超えてしまい、未払い利息が発生するおそれもあります。
未払い利息とは、金利の見直しで適用金利が引き上げられることによって生じる、返済額よりも利息の額が上回った際の、その上回る部分のことです。
変動金利の5年ルールと125%ルール
変動金利でかつ元利均等返済を選択した場合、一般的に「5年ルール」と「125%ルール」が設けられています。
「5年ルール」とは、借入期間中に金利の変更があった場合も5年間返済額は一定のまま、返済額の内訳である元金と利息の金額が各々変更となり、毎月の返済額自体の見直しは5年ごとに行われる、といったルールです。
「125%ルール」とは、5年ごとに行われる毎月の返済額自体の見直しにおいて、借入金利が上昇して返済額が増額になった場合でも、現在の返済額の125%以上にはならない、といったものです。
これらのルールは金利上昇による返済額の急激な変化を防ぐためのルールです。しかし、5年ルール・125%ルールによって減額された部分は支払わなくて良い、ということではありません。住宅ローン契約の最後に一括で返済する必要が出てきたり、未払い利息が発生したりする可能性があることに注意しましょう。
固定金利(全期間型)
固定金利(全期間型)は、その名のとおり、契約時から返済終了まで金利が変わらないタイプです。代表的なものとして「フラット35」があります。
固定金利は金利水準に左右されないため、万が一金利が急上昇しても適用される金利は一定です。そのため、住宅ローンを完済するまで毎月の返済額が変わりません。
住宅ローンを組んだ時点で総返済額がはっきりとわかるため、返済計画を立てやすいというメリットもあります。
ただし、一般的に適用金利は変動金利よりやや高めに設定されています。
固定金利(期間選択型)
固定金利(期間選択型)は、契約時に選んだ適用期間は金利が変わらないタイプです。固定金利期間には、2年、3年、5年、10年などがあります。
このタイプの住宅ローンは、固定金利期間中に優遇金利を設定していることが一般的です。そのため、契約当初の数年間は低金利でローンを借入れできます。
固定金利期間を終えると、再度金利タイプを選択することになります(自動で変動金利へ移行するケースもあります)。どちらにしても、固定金利期間中に金利が上昇していれば、その後の返済額に影響を及ぼすことになるでしょう。
住宅ローンの金利を変更するタイミング
住宅ローンの返済期間は、20年や30年など長期にわたることが一般的であるため、わずかな金利差でも総返済額に大きな影響を与えます。
契約当時はご自身の条件に合った住宅ローンだったとしても、市場動向や金利情勢の変化によって、数年の間に条件に合わない金利だと感じるようになる可能性も十分にありえます。
そこで、住宅ローンの金利変更を検討するのに適したタイミングを解説します。
変動金利で返済額が気になったとき
先述のとおり、変動金利タイプの住宅ローンは、原則として5年ごとに、月々の返済額が見直されます。
半年ごとに実施される適用金利の変更にはさほど意識は向かなくても、毎月出ていくお金の変化は気になるものです。新たな金額での返済がいざ始まってみたら、思ったよりも負担が大きいと感じる方もいるでしょう。
このように、返済額が負担になったときも、ライフプランに合った金利へ変更するタイミングといえます。
固定金利の固定金利期間が終わったとき
期間選択型の固定金利で住宅ローンを利用中の方は、固定金利期間が終わったタイミングで金利が変わります。
ほとんどの金融機関で、固定金利期間は優遇金利が適用されています。そのため、優遇が終わったとたんに適用金利がアップし、毎月の返済額が想定以上に上がることも珍しくありません。
固定金利期間の終わりが近づいた時点で住宅ローン契約を確認し、以降の適用金利を把握することが大切です。
条件のよい住宅ローンをみつけたとき
低金利が続くなか、適用金利を抑えた住宅ローンが増えています。条件のよい住宅ローンをみつけたら、借換えによる金利の変更も検討しましょう。
わずか年1%の金利差でも、住宅ローンの総返済額を大きく減らせる可能性があります。
例えば、ローン残高2,000万円(返済期間残り20年)で金利年1.5%の住宅ローンを契約中の方が、金利年0.5%のローンに借換えたとします(元利均等、適用利率は固定)。
auじぶん銀行のシミュレーションによると、この年1%の金利ダウンによって月々の返済額は約97,000円から約88,000円へ、約9,000円も下げられます。
住宅ローンの金利を変更する方法
住宅ローンで金利を変更する方法には、変動金利から固定金利あるいは固定金利から変動金利へと金利タイプを変更する方法と、異なる金融機関で住宅ローンを借換える方法があります。
どちらの方法にもメリットとデメリットがあるので、金融機関の提示する金利や適用条件を確認のうえ、複数の住宅ローンを比較・検討するとよいでしょう。
それでは、住宅ローンの金利を変更する方法について、それぞれの特長を具体的に解説します。
同じ金融機関で金利タイプを変更する
現在住宅ローンを契約している金融機関で、金利タイプを変える方法があります。
すでに契約中の金融機関ということもあり、他の金融機関へ借換えをするよりも手続きが簡単に行えることが大きなメリットです。
ただし、固定金利から変動金利へ変更する場合、多くの金融機関で、固定金利期間中はプラン変更できません。また、低金利だと思って変更した変動金利が、上昇に転じるおそれもあります。
なお、変動金利から固定金利へ変更する場合、新規借入れよりも金利が高めに設定されているケースもあり、必ずしも有利な金利で契約できるとは限りません。
借入れている金融機関によって、金利タイプ変更のルールが異なりますので、事前にしっかり確認するようにしましょう。
異なる金融機関の住宅ローンへ借換える
現在とは異なる金融機関で住宅ローンを借換えることも、金利を変更する方法の一つです。とくに固定金利期間中でプラン変更ができない場合は、金利を変更する唯一の方法となります。
住宅ローンの借換えの手続きは、基本的に、新規の申込みと変わりません。事前審査、本審査を経て契約を交わし、融資が行われます。
違いは融資される資金が、物件の購入費用ではなく、契約中の金融機関への借入金の一括繰上返済に使われることです。
借換えなら、新規契約と同じ低金利が見込めます。一方で、契約にかかる諸費用の支払いや手続きの手間などもあることを、考慮しておきましょう。
金利を下げる優遇サービスにも注目
金融機関ごとにさまざまな金利優遇サービスを実施しているので、上手に活用して、契約はそのままに金利を変更するのもおすすめです。
例えば、auじぶん銀行の「au金利優遇割」では、au回線とじぶんでんきのセット契約で年0.289%(全期間引下げプラン・変動金利、2023年1月適用時)の優遇を受けられます。
他にも、契約者の出産や子どもの誕生・成長にあわせて金利が優遇されるサービスを提供している金融機関もあります。
住宅ローンの金利を変更する際の注意点
住宅ローンの金利の変更を検討する方のほとんどが、現在の契約よりも金利を下げて、返済額を抑えたいという希望をお持ちでしょう。
実際、金利タイプの変更や住宅ローンの借換えで、希望を叶えることは可能です。しかし、思わぬ理由から、かえって負担増となるケースもあります。
住宅ローンの金利変更で失敗しないために、気を付けておきたいポイントを紹介します。
金利情勢を読み違える
今後の金利上昇を見込んで、変動金利から固定金利への変更を考える方もいるでしょう。
しかし、予想に反して低金利が長く続けば、金利を変更する前よりも返済額が増えます。
予想と現実のギャップをできるだけ埋めたい場合は、変動金利はより低金利の変動金利に、固定金利はより低い固定金利になど、同じ金利タイプで変更するのがおすすめです。
手数料がかかる
金利プランの変更では、金融機関や申込方法によって手数料が発生する可能性があります。手数料が発生する場合、11,000円程度が一般的です。
また借換えでは、新規契約時と同じように、取扱い手数料や保証料、抵当権設定時の登録免許税など、さまざまな諸費用がかかります。
さらに、融資を受けた後に行う一括繰上げ返済では、数万円の手数料が必要な場合もあります。
金利の変更に関わる詳細な条件や費用について、あらかじめ確認しておくと安心です。
住宅ローン控除の対象外になる
住宅ローン控除の対象の場合、住宅ローンの借換えによって、控除の対象外になる可能性があります。
住宅ローン控除を利用したい場合は、次の2点の条件を満たすように契約内容に気を付けましょう。
- 借換えた住宅ローンが、明らかに元の住宅ローンを完済するためのものであること
- 例えば完済までの期間が10年以上あるなど、借換えた住宅ローンが控除要件を満たしていること
また、借換えによって金利が下がっても月々の返済額を同程度とした場合、これまでよりも元金返済のペースが早まります。そのため控除金額に影響が発生する可能性も考えられます。
住宅ローンの金利の変更はリサーチが必要
住宅ローンの金利は、タイプ変更や他金融機関への借換えによって契約後でも変えられます。変動金利で想像以上に返済額が上がったときや、固定金利の優遇金利が終わったタイミングなど、状況に応じた検討がおすすめです。
ただし、金利の変更でかえって総返済額が増える、借換えにかかる手数料や手続きが負担になるなど、デメリットを生じることもあります。
金融機関ごとに条件の違いもあるため、事前に十分にリサーチしましょう。