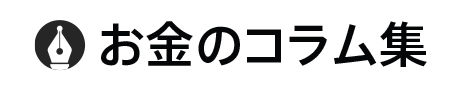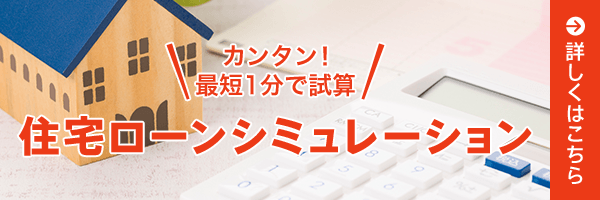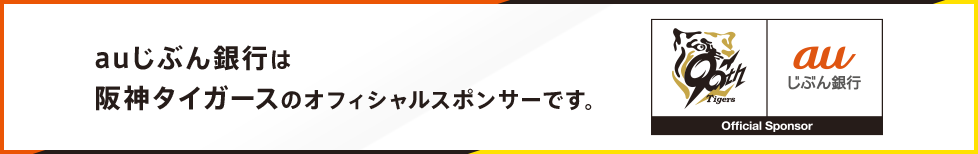2022/12/14
ペアローンにかかる諸経費は?一般的な住宅ローンとのコストの違いを解説!
監修者:新井 智美

住宅ローンの契約方法のひとつに、「ペアローン」があります。2人分の収入が金融機関の審査対象となるため、単独で申込むよりも大きな融資を受けやすくなり、マイホームを選ぶときの予算の幅も広がるでしょう。
この記事では、ペアローンの概要のほか、一般的な住宅ローンとは異なる諸経費(諸費用)の負担についてわかりやすく解説します。
ペアローンとは
ペアローンとは、ひとつの物件に対して2名がそれぞれに住宅ローンを組み、お互いが相手の連帯保証人となる仕組みです。対象の物件はひとつでも、住宅ローンの契約はふたつになるのが特長です。
一般的に、ペアローンの利用にあたっては、「対象となる物件は2名の共有名義」、「2名の関係は配偶者もしくは親子関係である」などといった利用条件が決められています。尚、利用条件は金融機関によって異なります。
収入合算との違い
ペアローンと似た住宅ローンの契約方法に、「収入合算」と呼ばれるものがあります。
収入合算とは、ひとつの物件に対して2名がそれぞれに住宅ローンを組むペアローンとは違って、住宅ローンの契約者はひとりです。ただし、夫婦や親子などの同居する親族が契約者の連帯保証人となることを条件に、契約者の収入に連帯保証人の収入を合算して、住宅ローンの審査を受けられます。
ペアローンを組む際に必要な諸経費
住宅ローンを利用するには、契約に関わるさまざまな諸経費を支払わなければなりません。諸経費はおおよそ数十万円~百数十万円程度と高額になることが多いです。住宅ローンを利用する際に支払う諸経費はご自身で用意するか、住宅ローンの借入金に含めることになります。ご自身で用意する場合はあらかじめ備えておくことが大切です。一方、住宅ローンの借入金に含める場合は、返済負担が増えてしまうことに注意しましょう。尚、住宅ローンの借入金に諸経費を含めることができるかについては金融機関や審査の結果によって異なります。
住宅ローンの契約方法にペアローンを選んでも、ひとつの物件に対する契約数が増えるだけで、支払う諸経費は一般的な住宅ローンと違いはありません。
ここでは、ペアローンを含めた住宅ローンの契約で、金融機関に支払う必要がある主な諸経費をお伝えします。
諸経費1:事務手数料(融資事務手数料)
住宅ローンの融資を実行する金融機関に対して支払う費用で、通常、融資を実行するタイミングで支払います。
諸経費2:保証料
保証会社から住宅ローンを保証してもらうための費用で、一括で前払いする「外枠方式」と金利に上乗せして支払う「内枠方式」があります。
保証会社を利用しない金融機関の場合は、保証料は不要です。
諸経費3:各種税金
住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)を作成するときに求められるのが印紙税です。
さらに、住宅ローンでは対象物件を担保として融資が実行されますが、抵当権の設定時には抵当権設定登記にかかる登録免許税も必要になります。
諸経費4:団体信用生命保険料
団体信用生命保険(団信)とは、死亡や高度障害などにより、契約者による住宅ローンの返済が困難になった場合、保険金により借入残金が全額完済される保険です。住宅ローン契約時(借換え時含む)のみ加入できます。
いわゆる一般団信と呼ばれる死亡・高度障害時のみを保障するスタンダードな団信であれば、団信保険料は住宅ローン金利にあらかじめ含まれているケースが一般的です。ただし、3大疾病や要介護などに対応する特約を付加する場合には、追加の保険料として金利が上乗せされることがあります。金融機関によって取扱い団信や保険料は様々なので、各金融機関のウェブサイトにてご確認ください。
ペアローンは諸経費が2人分かかる?
契約方法にかかわらず、住宅ローンにかかる諸経費の種類には基本的に差はありません。つまり、ペアローンを選んだからといって、特別な費用は発生しないのです。それにもかかわらず、ペアローンで住宅ローンを組むと、単独で契約するよりも諸経費の支払いが増えてしまいます。
その理由は、ペアローンでは住宅ローンの契約が2本に増えるためです。
ペアローンは、ひとつの物件に対し、ふたつの住宅ローンを組むことになります。そのため、契約1本に対して発生する各種税金については2本分、つまり2倍かかります。一方、事務手数料や保証料については、借入金額に応じて金額を設定する場合はペアローンだからといって諸経費が増えることはありません(もちろんペアローンにすることによって借入金額が増えれば、支払う事務手数料・保証料も高くなります)。しかし、契約1本に対して事務手数料・保証料が決められている場合は諸経費が増えることになります。
金融機関によって異なる部分ですので、必ず各金融機関へ確認しましょう。
ペアローンには返済リスクもある
団体信用生命保険(団信)は、契約者に万が一の事態が起こったとき、残された家族にとって大きなお守りとなります。しかし、ペアローンでは契約者ごとに団体信用生命保険(団信)に加入するため、どちらかひとりが亡くなったとしても、保険金で返済されるのは死亡者名義の住宅ローンのみになりますので、もうひとりの住宅ローンの返済は続きます。
ひとりで返済を続ける可能性も考慮してそれぞれの借入金額を考える、団体信用生命保険(団信)のほかに生命保険への加入を検討するなど、ライフプランや収入、健康状態に合ったペアローンの利用を検討しましょう。
ペアローンの諸経費を抑える方法
2つの住宅ローン契約が必要となることから、単独での契約よりも諸経費がアップすることは免れないペアローンですが、節約につながるポイントはあります。それでは、ペアローンで諸経費を抑える方法を紹介します。
事務手数料の安い金融機関を選ぶ
住宅ローンの事務手数料(あるいは融資手数料)は、金融機関によって金額が異なります。少しでも諸経費を抑えるのならば、事務手数料の安い金融機関を選ぶようにしましょう。
ただし、事務手数料が安くても保証料が高い、保証料が0円でも事務手数料が高い、など、部分的には割安でもトータルでみると諸経費が高くなるケースもあります。逆に、住宅ローンの金利は高めでも、諸経費が抑えられている場合もあるでしょう。
必要となる諸経費をもれなく確認し、いくつかの金融機関を比較・検討するのがおすすめです。
保証料を節約する
住宅ローンでかかる諸経費のなかでも、とくに高額とされるのが保証料です。保証料の金額は、借入金額や返済期間によって決まります。そのため、できるだけ自己資金を用意して借入金額を減らし、返済期間を短めに設定することが、節約につながります。
先述の通り、保証料の支払い方法には、一括で現金を前払いする外枠方式と、住宅ローン金利に上乗せする内枠方式があります。外枠方式にすると初期費用の負担が大きいですが、諸経費を含めたトータルの返済額は内枠方式より抑えられることが多いようです。手元のキャッシュに余裕があるなら、保証料は一括前払いをおすすめします。
外枠方式を選んだ場合で、設定していた返済期間よりも早く完済できる場合は、完済時に保証料が精算され返還されます。
諸経費を安く抑えてペアローンを賢く活用しよう
住宅ローンは、個人の年収や勤務歴、ほかのローンの利用状況などによって借入金額が決まります。もし希望する借入金額に達しないようなら、夫婦や親子でペアローンを組むことも、マイホーム購入の夢をかなえる方法のひとつでしょう。
ただし、ペアローンはひとつの物件に対して、ふたつの住宅ローンを契約することになるため、諸経費が多くかかります。返済金額だけではなく、諸経費にかかるコストも確認しておくことが大切です。