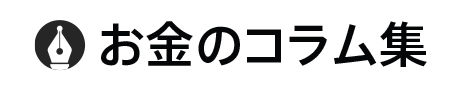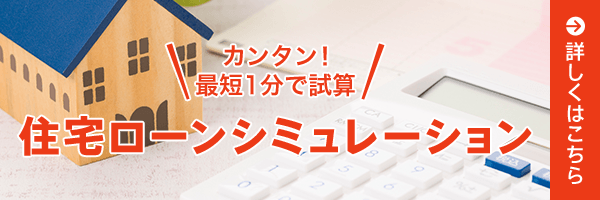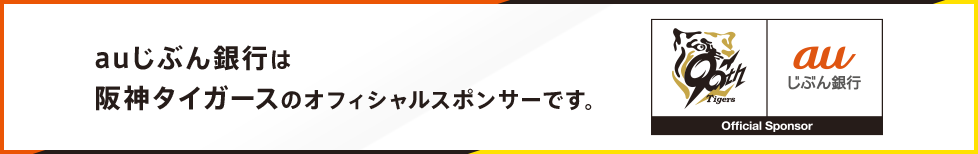年収からみる住宅ローンの借入可能額の目安やポイント、決まり方を解説!
監修者:淺井 敏次(ファイナンシャルプランナー)
2022年8月15日

住宅ローンをいくらぐらい借りられるかを考えるとき、年収は判断基準のひとつとされます。この記事では、年収からわかる住宅ローン借入可能額の目安や具体的な決まり方などを解説します。
年収からみる住宅ローンの借入可能額の目安
住宅ローンを利用するとき、年収をもとに借入可能額を判断する話を良く聞きます。実際、金融機関による住宅ローンの審査で年収は重要な要素になるため、借入可能額の目安を知るのに適した判断材料といえます。
なお、年収は支給額のことで、所得税や住民税、社会保険料なども含まれるため、実際の手取とは違います。
それでは、年収から住宅ローンの借入可能額の目安を考える方法を解説します。
年収倍率でみる新築物件の所要資金は?
住宅金融支援機構による「2020年度フラット35利用者調査」によると、新築物件の年収倍率は、土地付注文住宅が7.4倍、マンションが7.0倍、建売住宅が6.8倍、注文住宅が6.7倍です(※)。
年収倍率は、住宅の購入価格=「所要資金」が購入者の世帯年収の何倍になっているかを示す指標です。(年収倍率=所要資金÷世帯年収数値)
所要資金は、注文住宅では予定建設費と土地取得費を合計した金額、新築住宅は購入価格です。
つまり、新築物件は戸建て・マンションとも、年収の約7倍がざっくりとした目安といえます。
例えば年収600万円で新築マンションの購入を検討する場合、年収の7倍にあたる4,200万円(600万円×7.0倍)が所要資金の目安となります。
- ※参考:住宅金融支援機構「2020年度フラット35利用者調査」https://www.jhf.go.jp/files/400357456.pdf 13ページ
住宅金融支援機構による調査対象は、全期間固定型住宅ローン「フラット35」利用者の年収倍率による所要資金です。変動型や固定期間選択型の住宅ローン利用者が含まれないため、必ずしも実態に見合った目安になるとは限りません。
住宅ローンの目安は年収の約5倍
住宅金融支援機構が実施した「住宅ローン利用者の実態調査」では、住宅ローンの返済負担率は15%以上20%以内が最多です(※)。
返済負担率とは、年収に対する住宅ローンの1年間の返済率のことです。例えば、年収600万円の方が月々のローン返済額を10万円とした場合、返済負担率は10万円×12ヶ月÷600万円=20%となります。
15~20%という返済負担率から、年収の5~6倍で住宅ローンを組む方がもっとも多いことがわかります。借入可能額を考えるときには、年収5~6倍もひとつの目安として覚えておくのがおすすめです。
「フラット35」は年収400万円以上の場合、総返済負担率は年収の35%までローンを組めますが、返済の安全なレベルは20%程度です。20%で35年借りると借入総額は年収の約7倍、30年なら約6倍、25年なら約5倍になります。
- ※参考:住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査」(2022年4月調査)https://www.jhf.go.jp/files/400361299.pdf 9ページ
年収でみる住宅ローンの借入可能額の早見表
年収からみる住宅ローンの借入可能額は、年収倍率や返済負担率から、5~7倍という目安を知ることができます。実際に「可能」な借入額を知るには、ご自身の年収からシミュレーションをするのが確実です。
ここでは、年収ごとに住宅ローンの借入可能額を計算し、早見表でわかりやすく紹介します。
住宅ローンの借入可能額
auじぶん銀行住宅ローンのシミュレーションより、年収ごとの借入可能額などを以下の表にまとめました。
https://www.jibunbank.co.jp/products/homeloan/simulator/
元利均等返済、全期間引下げプラン・変動金利年0.41%(2022年8月金利)(ボーナス月の増額返済なし)、35年返済で算出しています。
| 年収 | 借入可能額 | 毎月の返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|---|
|
300万円 |
2,340万円 |
59,816円 |
25,122,876円 |
|
400万円 |
3,120万円 |
79,755円 |
33,497,244円 |
|
500万円 |
3,910万円 |
99,950円 |
41,978,948円 |
|
600万円 |
4,690万円 |
119,889円 |
50,353,295円 |
|
700万円 |
5,470万円 |
139,828円 |
58,727,666円 |
|
800万円 |
6,250万円 |
159,767円 |
67,102,024円 |
借入可能額は約8倍弱です。
借入可能額の結果をみて、意外とたくさん借りられると感じた方もいるかもしれません。しかし、この金額はあくまでも金融機関が審査対象とする「可能額」のため、毎月の返済額や総返済額も確認しながら慎重に決めることが大切です。
年収5倍の借入金額と比較
住宅ローンの利用実態に近い借入倍数5倍の場合の借入金額による表も確認しましょう。計算条件はさきほどと同じです。
| 年収 | 借入額 | 毎月の返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|---|
|
300万円 |
1,500万円 |
38,344円 |
16,104,300円 |
|
400万円 |
2,000万円 |
51,125円 |
21,472,498円 |
|
500万円 |
2,500万円 |
63,906円 |
26,840,690円 |
|
600万円 |
3,000万円 |
76,688円 |
32,208,860円 |
|
700万円 |
3,500万円 |
89,469円 |
37,577,051円 |
|
800万円 |
4,000万円 |
102,251円 |
42,945,202円 |
所要資金に足りないと感じたり少なすぎると思われたりする方もいるでしょう。その場合、現在支払っている賃貸料と毎月の返済額を比較して、ご自身に適した借入金額かどうかを判断する方法もあります。
住宅ローンの借入金額をどう決める?
借入金額の目安はわかっても、住宅ローンを組むにあたって希望額を決めるのはむずかしい決断です。そこで、住宅ローンの借入金額を決めるときのポイントを解説します。
頭金をどれだけ用意できるかがポイント
住宅ローンの借入金額は、無理なく返済できる金額にすることが重要です。そのためにも、年収や総返済額、ライフプランなどからじゅうぶんに検討する必要があります。
もうひとつ、借入金額の決定を左右する要素となるのが、頭金の有無と金額です。
一定の要件を満たしたうえで住宅ローンを借り入れると、所得税の控除を受けられます(住宅ローン控除)。住宅ローン控除の恩恵を受けようと、頭金ゼロのフルローンが選ばれることも珍しくありません。
しかし、頭金の割合で金利が高くなる住宅ローンもあるなど、頭金ゼロによるデメリットにも注意です。また、頭金が少ないほど借入金額が増え、当然ながら毎月の返済額や総返済額などの負担が大きくなります。
金利の動向や今後のライフイベントを見据え、頭金を考慮しながら借入金額を決めましょう。
住宅ローンの借入可能額まで借りても大丈夫?
住宅ローンの借入可能額は、金融機関の商品内容や審査基準、他のローンの利用状況などによって異なります。ただし、金融機関の審査に通ったのであれば借りることに問題はありません。
しかし、借入可能額は審査に通る最高額であって、利用する方にとって適切な金額とは限りません。もし返済に無理のある金額であれば、返済が滞る、生活が苦しくなるなどのリスクとなります。
住宅ローンを利用するときは、借入できる金額と返済できる金額が違うことを認識しておくことが大切です。各種住宅ローンサイトで具体的なシミュレーションを行うなどして、無理のない借入金額で契約しましょう。
また、住宅ローンの返済期間は長期にわたります。会社の倒産や離婚など予期せぬトラブルが起こる可能性もゼロではないので、ゆとりある計画を意識してください。
住宅ローンは年収で目安をつけてから無理のない借入可能額を設定しよう
住宅ローンは年収から借入限度額の目安をつけられます。しかし、借りたお金は必ず返済しなければなりません。
事前にシミュレーションを行うなどして、無理のない借入にすることが大切です。