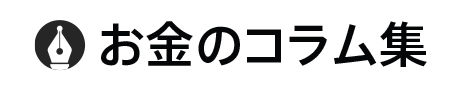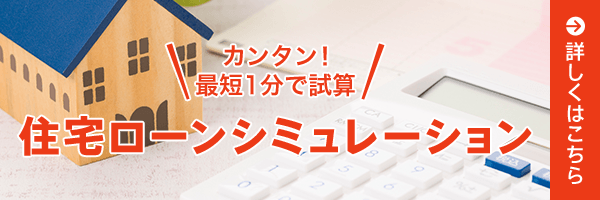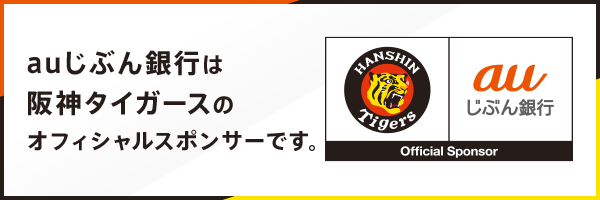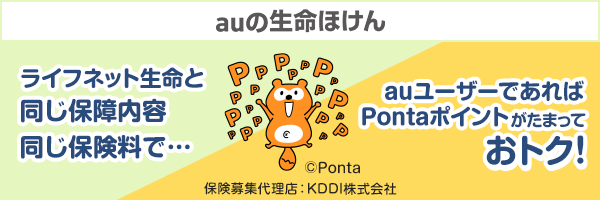2023/07/26
住宅ローン控除で住民税の減税ができる?基本的な仕組みや控除の条件を解説
監修者:新井 智美

住宅ローン控除は、住宅ローン利用者を対象に「所得税を控除」する制度です。しかし、場合によっては「住民税の控除」も受けられます。そこで、本記事では2023年7月時点の住宅ローン控除の仕組みや住民税が安くなる条件などを解説します。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築や取得、あるいは増改築などをしたときに、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を原則として所得税から控除する制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、住宅ローン減税と呼ばれることもあります。
住宅ローン控除の適用期間は2025年12月31日までに対象の住宅に入居分までで、控除期間は最大13年(既存住宅の増改築は最大10年)です。
住宅ローン控除が適用されるには、住宅ローンの返済期間が10年以上ある、控除を受ける本人が居住するための住宅であるなど、一定の条件を満たす必要があります。
2022年に行われた税制改正では、新築住宅に対する適用ルールが変更されています。これまで、環境に配慮された住宅は一般の住宅より借入限度額の設定を高くする優遇策が取られてきました。しかし、2024年1月1日以降に新築の建築確認を受けた住宅、あるいは2025年6月30日以降に建築された住宅は、省エネ基準を満たさなければ住宅ローン控除の対象外となるためご注意ください。
住宅ローン控除の仕組みや適用条件など、詳しくは以下を参考にしてください。
住宅ローン控除で住民税が安くなる?
先述の通り、住宅ローン控除は原則として所得税からの控除に関わる制度です。しかし、所得税額よりも住宅ローン控除額の方が多いと所得税から控除しきれません。
その場合は、一定の条件のもと、住民税からも控除ができます。
所得税で控除しきれないことはありうる?
住宅ローン控除可能額を所得税から控除しきれなくなる可能性を、具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。
住宅を新築したときの借入限度額や控除期間の条件
| 区分 |
居住年 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
| 認定長期優良住宅 (長期優良住宅) |
5,000万円 |
4,500万円 |
||
| 認定低炭素住宅 (低炭素建築物、低炭素建築物とみなされる特定建築物) |
||||
| ZEH水準省エネ住宅 (特定エネルギー消費性能向上住宅) |
4,500万円 |
3,500万円 |
||
| 省エネ基準適合住宅 (エネルギー消費性能向上住宅) |
4,000万円 |
3,000万円 |
||
| その他の住宅 (一般の新築住宅) |
3,000万円 |
0万円 |
||
- ※2023年12月31日までの建築確認を受けた住宅、あるいは2024年6月30日までに建築された住宅が対象。ただし、特例居住用家屋は2023年12月31日までに建築確認を受けたもののみ
例えば、年収500万円の方が住宅ローンの諸条件を満たした「ZEH水準省エネ住宅」に、2023年に入居したとします。住宅ローンで借入限度額4,500万円を利用しその年の年末残高が4,400万円のとき、1年あたりの住宅ローン控除額は「4,400万円×0.7%=30万8,000円」です。
次に、年収500万円の所得税を求めます。収入から差し引かれる各種控除を次のように設定します。
- 基礎控除(本人):38万円
- 配偶者控除(妻):38万円
- 扶養控除(19歳以上23歳未満の大学生):63万円
- 生命保険料控除:10万円
すると、課税所得は「収入500万円-控除合計149万円=351万円」です。
国税庁「所得税の速算表」より、課税所得351万円の所得税率は20%、控除額は42万7,500円なので、所得税額は「351万円×20%-42万7,500円=27万4,500円」です。
「住宅ローン控除額30万8,000円-所得税額27万4,500円=3万3,500円」となり、住宅ローン控除額が所得税額を上回っています。
このように、年収や控除の種類によっては所得税から住宅ローン控除可能額を控除しきれない可能性は十分にあると予測できます。
住民税の住宅ローン控除を受ける条件
住民税から控除される金額には上限があり、次のいずれかのうち少ない方と決まっています。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち控除しきれなかった金額
- 所得税の課税所得金額の5% (上限97,500円)
ただし、2014年4月から2021年12月(特別特例取得などに該当するなら2022年12月)までに入居し、対象住宅の取得にかかった消費税の税率が8%または10%の場合は、住宅ローン控除の上限は所得税の課税所得金額の7%(上限13万6,500円)です。
詳しい控除条件は、ご自身の居住地の市区町村に確認すると安心です。
住民税の住宅ローン控除を受けるための手続き
住民税から住宅ローン控除を受けるために必要な手続きは、特にありません。住民税は地方自治体の管轄ですが、市区町村への申告は不要です。
住宅ローン控除は、初年度は確定申告、2年目以降は会社員が年末調整、個人事業主や自営業者が確定申告によって手続きします。ただし、医療費控除や副業等をしている会社員の方の場合は、確定申告が必要です。
年末調整や確定申告で提出された書類のうち、住宅ローン控除額を確認する書類は税務署から市区町村へ回り、共有できるため、年末調整あるいは確定申告を終えていれば、市区町村へあらためて届出る必要はありません。
住民税の住宅ローン控除を受けるときの注意点
住民税の住宅ローン控除は、住宅ローン控除に必要な手続きをしていれば追加の手続きは不要です。しかし、住民税の住宅ローンを受けるときに注意したい点があります。
- 所得税と住民税では税額控除の形が異なる
- ふるさと納税の手続き方法で税額に違いがある
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
所得税と住民税では税額控除の形が異なる
原則として所得税から控除される住宅ローン控除ですが、所得税の場合は「還付金」として申請者が指定する口座に入金されます。還付されるタイミングは申告からおおむね1ヶ月~1ヶ月半ほどで、電子申告(e-tax)の場合は3週間ほどです。なお、2年目以降は勤務先の年末調整で還付金を受取ることができます。
しかし、住民税から住宅ローン控除を受けると現金の還付はありません。その代わり、翌年に課される住民税の所得割から控除された分が減額されます。
住民税の納税通知書は、会社員であれば毎年5月頃に市区町村から会社へ、フリーランスや自営業者であれば毎年5~6月頃に市区町村から本人へ発送されます。
住民税から住宅ローン控除を受けたときには、翌年5~6月頃の納税通知書で控除額を確認しましょう。
ふるさと納税の手続き方法で税額に違いがある
ふるさと納税とは、ご自身で選択した自治体に寄付するかわりに、自己負担額2,000円を除き、所得税と住民税が控除される制度です。各地の特産品を返礼品として受取れるとあり、ふるさと納税の受入額・受入件数は毎年上昇傾向にあります。
ふるさと納税と住宅ローン控除の併用はできますが、納税額からの控除(還付)となり、納税額以上は控除できないのでロスが生じる可能性があります。
ふるさと納税で控除を受けるためには、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」または「確定申告」のいずれかの方法で手続きする必要がありますが、確定申告で手続きする方は特に控除額にご注意ください。
会社員を対象とする、ふるさと納税ワンストップ特例制度でふるさと納税の手続きをすれば、ふるさと納税による控除はすべて住民税額から行われます。
しかし、確定申告で手続きすると所得税額からも一部控除されます。そのため、ふるさと納税をした分だけ所得税額が減り、所得税から控除できる住宅ローン控除額が減ってしまいます。
控除しきれない分は住民税から控除できますが、上限は課税所得金額の5%(上限97,500円)までのため、住民税でも控除しきれないケースが考えられます。
確定申告が必須となる住宅ローン控除の利用初年度は、ご自身が利用している制度による所得税控除額の総額を確認しましょう。
住宅ローン控除を活用する際は住民税から控除されるケースも確認しよう
住宅ローン控除は、所得税から控除しきれない場合に住民税からも控除ができます。年末調整や確定申告など、住宅ローン控除を受けるのに必要な手続きを行えば、住民税からの控除には特別な手続きはいりません。
2025年末まで延長された住宅ローン控除について十分に理解し、住宅ローン控除の適用を適切に受けましょう。