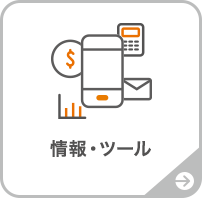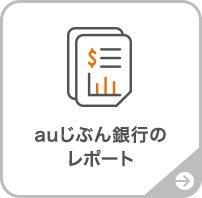更新日 : 2025年07月13日
今週の見通し
2025年07月14日~2025年07月18日(145.80円~148.30円)
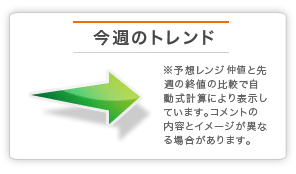
- 上げ渋りか、米インフレ加速も成長鈍化を警戒
- 上げ渋りか。7月15日発表の6月消費者物指数(CPI)が手掛かり材料となりそうだ。総合、コア指数が5月実績を上回った場合、早期利下げ観測は一段と後退する見込み。ただ、物価高によって個人消費は減退し、米国経済の大幅な減速も警戒されており、米ドル・円は148円近辺で上げ渋る展開もあり得る。
先週の動き
2025年07月07日~2025年07月11日(144.23円~147.52円)
- 上昇、米国の関税措置を意識してドル買い強まる
- 上昇。トランプ米大統領は日本や韓国からの製品に25%の関税を課すと述べたことが意識された。米国側では関税による物価高が警戒されているが、日本側では対米輸出の減少によって国内総生産(GDP)は減少するとの見方が増えている。米国の7月利下げ観測は後退し、米長期金利は上昇したこともドル買い材料となった。
バックナンバー
2025年06月30日~2025年07月04日の動き
- もみ合い。米7月利下げ観測後退でドル売り弱まる
- もみ合い。7月3日に発表された6月米雇用統計や6月ISM非製造業景況指数が予想を上回り、7月利下げ観測が一段と後退した。ただ、トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長に対してすみやかな利下げを改めて求めたことから、リスク選好的な米ドル買い・円売りは一服した。
2025年06月23日~2025年06月27日の動き
- 弱含み、中東情勢安定化で安全逃避のドル買い縮小
- 弱含み。米国によるイラン核施設への攻撃を受けて安全逃避の米ドル買い・円売りが先行した。しかしながら、トランプ米大統領がイスラエルとイランの停戦合意成立を発表したことを受けて、安全逃避的な米ドル買い・円売りは縮小。米国の9月利下げ観測も浮上し、6月26日の欧米市場で一時144円を下回った。
2025年06月16日~2025年06月20日の動き
- 上昇、中東情勢悪化で安全逃避のドル買い強まる
- 上昇。中東情勢の緊迫化や株安を警戒して週初に143円台後半まで米ドル安円高に振れる場面があった。しかしながら、中東情勢の悪化や原油高を意識した米ドル買い・円売りが強まり、6月20日の取引で5月下旬以来となる146円台前半まで米ドル高円安が進行した。
更新日 : 2025年07月13日
今週の見通し
2025年07月14日~2025年07月18日(170.50円~173.50円)
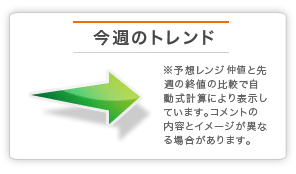
- 伸び悩みか、日本の政治不安を警戒
- 伸び悩みか。欧州中央銀行(ECB)の利下げサイクル休止の思惑が一段と広がっている。ユーロ圏の経済指標で景況感の改善が示された場合、ユーロ売りは弱まりそうだ。ただ、7月20日投開票の日本の参院選を巡って政治不安が高まっている。リスク回避の円買いが増えた場合、ユーロ・円相場を下押しする展開もあり得る。
先週の動き
2025年07月07日~2025年07月11日(169.88円~172.42円)
- 堅調推移、日欧金利差は当面維持される可能性
- 堅調推移。昨年7月以来となる172円台に上昇。欧州中央銀行(ECB)は最近におけるユーロ高を特に懸念していないこと、米国の関税措置を受けて米ドル買い・円売りが活発となったことが要因。日欧金利差は当面維持される可能性は高いことも、ユーロ買い・円売りにつながったようだ。
バックナンバー
2025年06月30日~2025年07月04日の動き
- 強含み、昨年7月以来となる170円台
- 強含み。昨年7月以来となる170円台に乗せた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は「為替レートは経済の強さを示す」との見方を伝えており、ECBによる利下げサイクルの終了予想が一段と広がったことが要因。日欧金利差がただちに縮小する可能性は低いこともユーロ買いにつながったようだ。
2025年06月23日~2025年06月27日の動き
- 強含み、中東情勢安定化を意識したユーロ買い
- 強含み。イスラエルとイランは停戦で合意し、中東情勢が改善したことが好感された。中東地域における地政学的リスク増大の懸念は和らぎ、安全逃避のユーロ売り・米ドル買いは縮小。米ドル・円相場は円高方向に振れたものの、ユーロは対円でしっかりとした値動きを見せた。
2025年06月16日~2025年06月20日の動き
- 堅調推移、原油高を意識したユーロ買い継続
- 堅調推移。中東情勢の悪化による原油高を受けてユーロ買い・円売りが次第に強まる展開となった。日本銀行による早期利上げの可能性は低いため、日欧金利差縮小観測は広がっていないこともユーロ買い・円売りを促す一因となった。
更新日 : 2025年07月13日
今週の見通し
2025年07月14日~2025年07月18日(95.00円~98.00円)
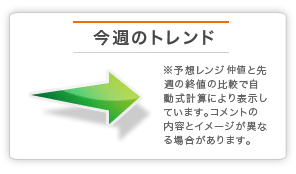
- もみ合いか、6月失業率が手掛かり材料に
- もみ合いか。豪準備銀行(中央銀行)は政策金利の据え置きを決定したが、今後の利下げ実施の可能性は残されている。7月17日発表の6月失業率が市場予想を上回った場合、将来的な利下げを想定した豪ドル売り・円買いがやや強まる可能性もあろう。
先週の動き
2025年07月07日~2025年07月11日(94.17円~96.76円)
- 上昇、政策金利据え置きで豪ドル買い強まる
- 上昇。豪準備銀行(中央銀行)は7月8日開催の理事会で政策金利の据え置きを決定、豪ドル買いにつながった。理事会メンバーの過半数がインフレ鈍化を裏付けるさらなる情報を待つことを支持した。世界経済の不確実性は低下しつつあり、リスク回避目的の豪ドル買いが縮小していることも影響したようだ。
バックナンバー
2025年06月30日~2025年07月04日の動き
- もみ合い、原油高や米国株高を意識した豪ドル買いも
- もみ合い。豪準備銀行(中央銀行)による追加利下げの可能性があり、豪ドルの上値抑制要因となっている。一方、原油先物の上昇や米国株高を意識した豪ドル買いが観測された。世界経済の不確実性は低下しつつあることで、リスク選好資産である豪ドルの支えとなっているようだ。
2025年06月23日~2025年06月27日の動き
- もみ合い、中東情勢安定化による株高を意識
- もみ合い。中東情勢の改善を受けてリスクオンの流れが強まり、リスク選好的な豪ドル買い・円売りが観測された。また、米国の9月利下げ観測が広がったことも豪ドル買いにつながった。ただし、原油相場が大幅に下落したことは豪ドル買い抑制につながり、対円での上昇幅は限られた。
2025年06月16日~2025年06月20日の動き
- 堅調推移、原油高で豪ドル売り縮小
- 堅調推移。中東情勢の悪化を警戒した豪ドル売り・円買いが観測されたが、原油高を意識して豪ドル売り・円買いは縮小し、一転して豪ドル買い・円売りがやや活発となった。週末にドル・円相場が円安方向に振れたことも豪ドル買い・円売りを促す一因となった。
更新日 : 2025年07月13日
今週の見通し
2025年07月14日~2025年07月18日(7.90円~8.40円)
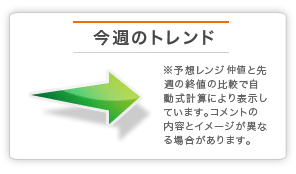
- もみ合いを予想、中国の景気動向に関心も
- もみ合いを予想。南アフリカは米国の高関税による先行き景気への警戒感が増す中、中国景気の持ち直しが下支えになってくるかに注目が向かう。そのため、7月15日に発表予定の4-6月期国内総生産(GDP)など、中国の経済指標に対する関心はこれまで以上に高まることが予想される。現状では大きな期待は持ちにくいか。
先週の動き
2025年07月07日~2025年07月11日(8.14円~8.29円)
- もみ合い、米関税策に警戒も
- もみ合い。世界的なリスクオンの流れ一服に加えて、トランプ米政権による南アフリカ輸入品への関税率30%が公表されたことで、景気の先行きに対する警戒感が強まる展開となった。先週は円も他通貨に対して売り優勢となったが、ランド・円の動きは鈍い状況となっている。
バックナンバー
2025年06月30日~2025年07月04日の動き
- 上昇、製造業PMIなど改善
- 上昇。6月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は48.5となり、前月の43.1から上昇している。景況感が改善に向かっているとして、ランドの買い材料につながったもよう。また、財新/S&Pグローバルが発表した6月の中国PMIも50.4となり、前月の48.3から上昇している。
2025年06月23日~2025年06月27日の動き
- もみ合い、円相場も対ドルなどで堅調推移となり
- もみ合い。世界的なリスクオンの流れ、米中通商協議の進展期待などはランド買い材料となるが、先週は円相場も対ドルや対ユーロで強い動きとなっており、ランド・円は横ばいにとどまった。米関税政策も絡み、南アフリカ景気の先行きに対する不透明感も依然として強いようだ。
2025年06月16日~2025年06月20日の動き
- もみ合いも強含み、円相場の軟調推移で
- もみ合いも強含み。日本銀行金融政策決定会合では、追加利上げを急がない姿勢が示され、円相場は他通貨に対して総じて軟調な推移となっている。これにより、ランド・円もやや買い優勢の流れとなった。中東情勢に対する過度な警戒感が緩和したことも、新興国通貨にとっては追い風か。
更新日 : 2025年07月13日
今週の見通し
2025年07月14日~2025年07月18日(87.70円~88.70円)
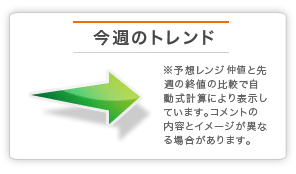
- 横ばいか、米長期金利の先高観測に歯止めを見込む
- 横ばいか。米国の6月消費者物価指数でインフレ率の高まりは確認されるだろうが、市場予想を大きく上回ることはないだろう。米関税政策への警戒感は根強いだろうが、米インフレ圧力と米長期金利の先高観測に歯止めがかかって円売りにも歯止めがかかるだろう。とりあえず円売り圧力が一巡し、対円でNZドルは横ばいへ。
先週の動き
2025年07月07日~2025年07月11日(87.13円~88.24円)
- 強含み、米長期金利の続伸で円売り
- 強含み。米関税政策への懸念で米インフレ圧力の高まりが意識されて米長期金利が上昇し、円売りが強まった。そうした中、NZの10年国債利回りは週間でやや弱含みとなったが、米長期金利を上回る水準にあることもあって、日本とNZの金利差拡大が意識されやすかった模様。対円でNZドルは買われ、週間で強含み。
バックナンバー
2025年06月30日~2025年07月04日の動き
- 横ばい、売り買いが交錯
- 横ばい。米国では6月雇用統計を中心に底堅い内容の米経済指標の発表が優勢だったため、米国経済減速への懸念が後退してリスク選好がやや優勢となり、円売りが優勢となる場面があった。しかし、週末に米関税政策への警戒感でリスク回避の売りがやや優勢となってリスク通貨NZドルが売られ、週間では対円で横ばいに。
2025年06月23日~2025年06月27日の動き
- やや強含み、リスク選好のNZドル買いがやや優勢に
- やや強含み。中東情勢への警戒感が和らぐ方向となった。これに伴う有事の米ドル買い一巡でNZドルと円は対米ドルで上昇したが、リスク選好がやや優勢となったため、リスク通貨NZドルの方がやや大きく上昇した。加えて日本銀行による早期の利上げ観測後退が円売り材料に。週間では対円でNZドルがやや強含み。
2025年06月16日~2025年06月20日の動き
- 反発、中東の地政学リスクがやや和らぎ、NZドル買い
- 反発。イランが核開発計画の協議再開を模索し始めていることが明らかに。イラン攻撃も辞さない姿勢を示唆したトランプ米大統領がイランとの協議再開の可能性とイラン攻撃の延期を表明した。これらの材料でリスク回避がやや和らぐ方向となり、リスク通貨のNZドルが安全通貨の円に対して買われ、反発した。
更新日 : 2025年07月13日
今週の見通し
2025年07月14日~2025年07月18日(25.91円~27.11円)
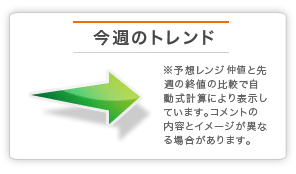
- 上値重いか、米国の高関税政策が引き続き圧迫材料へ
- 上値重いか。米国がブラジルに対して50%の高関税を課す方針が引き続き圧迫材料となろう。また、株式市場が下落した場合、レアル需要は縮小も。一方、成長予想の上方修正が支援材料となろう。また、中国当局が一連の景気対策を追加で発表したことも好感される見通しだ。
先週の動き
2025年07月07日~2025年07月11日(25.99円~27.01円)
- 弱含み、対米ドルの下落や米国の高関税政策で
- 弱含み。レアルの対米ドルの下落が対円レートを圧迫した。また、米国の高関税政策もレアルの売り圧力を強めた。トランプ米大統領は各国との関税交渉をめぐり、ブラジルに50%の関税を課す方針を示した。一方、レアルの下値は限定的。円安進行が対円レートをサポートした。また、原油価格の上昇も支援材料となった。
バックナンバー
2025年06月30日~2025年07月04日の動き
- 反発、株高や米中通商対立の緩和観測で
- 反発。株式市場の大幅上昇がレアル需要を高めた。また、米中の通商対立に緩和の兆しが出ているとの観測も輸出伸びの加速期待を高めた。ほかに、原油価格の上昇などが支援材料。一方、米利下げ期待がやや後退していることがレアルの圧迫材料となった。また、弱い経済指標も懸念された。
2025年06月23日~2025年06月27日の動き
- 弱含み、円高進行や株安などで
- 弱含み。円高進行が対円レートを押し下げた。また、株式市場の下落もレアル需要を縮小させた。このほか、原油価格の大幅安がレアルの圧迫材料となった。一方、レアルの下値は限定的。米中の金融緩和への期待感などがレアルの支援材料となった。また、中東地域の安定化観測も好感された。
2025年06月16日~2025年06月20日の動き
- 反発、円安進行や成長予想の上方修正で
- 反発。円安進行が対円レートを押し上げた。また、成長予想の上方修正も好感された。2025年の成長予想は前回調査の2.18%から2.20%に引き上げられた。ほかに、原油価格の上昇などが支援材料。一方、中東情勢の不透明感などがレアルの上値を抑えた。
更新日 : 2025年07月13日
今週の見通し
2025年07月14日~2025年07月18日(20.30円~20.58円)
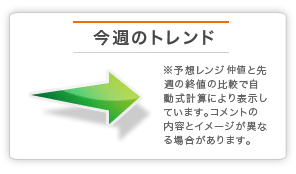
- 弱含みか、中国の6月経済指標が弱めで売りが優勢へ
- 弱含みか。注目材料の米国の6月消費者物価指数でインフレ率の高まりが確認されるだろうが、概ね市場予想並みに止まるとみる。米長期金利の先高観測に歯止めがかかり、対米ドルでの円売りが一服へ。反面、中国の6月経済指標が弱めで中国経済の減速懸念が人民元売り材料となるだろう。週間では対円で人民元は弱含みへ。
先週の動き
2025年07月07日~2025年07月11日(20.12円~20.57円)
- 上昇、対円で米ドルに連れ高
- 上昇。米関税政策への警戒感から米インフレ圧力の高まりが意識されて米長期金利が続伸した。これを受けて対米ドルでの円売りが強まった。人民元は中国人民銀行(中央銀行)が設定する対米ドル基準値を中心に売買されるため、米ドルとの連動性がある。週間では人民元は米ドルに追随する形で対円で上昇した。
バックナンバー
2025年06月30日~2025年07月04日の動き
- 横ばい、リスク選好後リスク回避
- 横ばい。木曜日に米国の6月雇用統計が底堅い内容で米国経済の減速懸念が後退するとリスク選好が緩やかに強まって安全通貨の円売りとリスク通貨の人民元買いが優勢に。週末に米関税政策への警戒感がやや強まるとともにリスク回避もやや強まって人民元売り・円買いが優勢となり、週間では対円で人民元は横ばい。
2025年06月23日~2025年06月27日の動き
- 弱含み、米ドル売りに追随して売られる
- 弱含み。イスラエルとイランの停戦合意を受けて有事の米ドル買いが一巡し、対円で米ドル売りが優勢に。対米ドル基準値をもとに売買される人民元は対円での米ドル売りに追随して売られた。ただ、中国人民銀行(中央銀行)が対米ドル基準値高め誘導の姿勢を維持したため、人民元は対円で米ドルほど売られず、週間で弱含み。
2025年06月16日~2025年06月20日の動き
- 上昇、対米ドル基準値の高め誘導が寄与し、買われる
- 上昇。中東情勢を巡る過度の警戒感が後退し、リスク回避がやや和らぐ方向となった。そうした中、世界最大の経済大国で軍事大国でもある米国の通貨米ドルが買い安心感から安全通貨の円に対して買われた。中国人民銀行(中央銀行)が対米ドル基準値の高め誘導をしているため、人民元も対円で買われ、週間で上昇した。
更新日 : 2025年07月13日
今週の見通し
2025年07月14日~2025年07月18日(10.60円~10.80円)
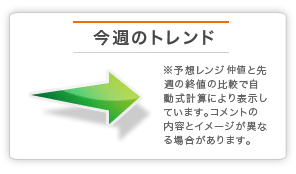
- 上値重いか、早期米利下げ期待の後退で
- 上値重いか。早期の米利下げ期待の後退がウォンなどの売り圧力を強めよう。また、米通商政策の不透明感も引き続き警戒される見通しだ。一方、中国当局が一連の景気対策を追加で発表したことが、対中輸出の拡大期待を高めよう。また、円安が一段と進行した場合、対円レートは続伸も。
先週の動き
2025年07月07日~2025年07月11日(10.55円~10.72円)
- 強含み、円安進行や米中関係の改善期待で
- 強含み。円安進行が対円レートを押し上げた。また、米中関係の改善が期待されていることも輸出伸びの加速観測を高めた。ほかに、株式市場の上昇がウォン需要を高めた。一方、米通商政策の不透明感などが足かせとなった。
バックナンバー
2025年06月30日~2025年07月04日の動き
- 強含み、経済指標の改善や米中通商対立の緩和観測で
- 強含み。経済指標の改善が好感された。6月の輸出入はそろって前月のマイナス成長からプラス成長に回復。また、米中の通商対立の緩和観測も支援材料となった。一方、ウォンの上値は重い。円高進行が対円レートを押し下げた。また、米利下げ期待がやや後退していることも嫌気された。
2025年06月23日~2025年06月27日の動き
- 弱含み、円高進行が足かせ
- 弱含み。円高進行が足かせとなった。また、内外景気の先行き不透明感も圧迫材料となった。一方、ウォンの下値は限定的。中東情勢の落ち着きが好感された。また、米中の金融緩和への期待感も、韓国市場への資金流入が加速するとの観測を高めた。
2025年06月16日~2025年06月20日の動き
- 強含み、株高や円安進行で
- 強含み。株式市場の上昇がウォン需要を高めた。また、円安進行も対円レートを押し上げた。ほかに、中国当局が追加の景気対策を打ち出すとの観測が好感された。一方、ウォンの上値は重い。中東情勢の緊迫化や米利下げの後ずれ観測などがウォンの上値を抑えた。

 米ドル
米ドル ユーロ
ユーロ 豪ドル
豪ドル ランド
ランド NZドル
NZドル レアル
レアル 中国元
中国元 ウォン
ウォン