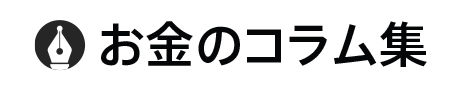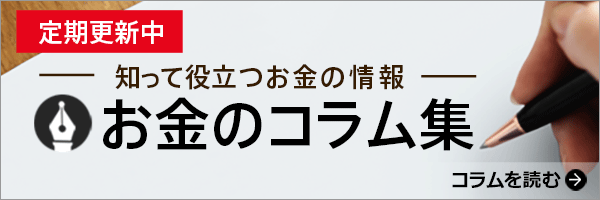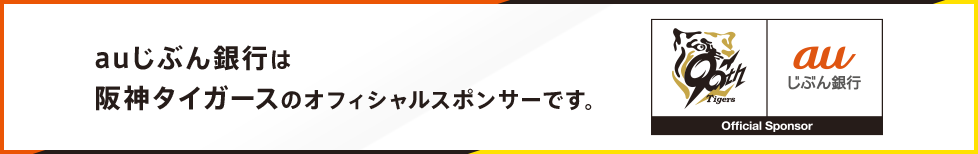2025/01/31
貯金2,000万円は必要? 年齢別の割合や貯めるまでの方法も紹介
執筆者:新井智美(ファイナンシャル・プランナー)

2019年ごろ、老後生活での収入が年金だけの場合、物価上昇のことも考えると最低でも2,000万円の貯金が必要といわれ、老後2,000万円問題が話題となりました。そのため、貯金2,000万円を目標としている人も多いのではないでしょうか。
とはいえ実際に2,000万円を貯めている人はどの程度いるのか、また2,000万円をどのように貯めたらいいのかわからないままでは、現実的な目標として立てられません。
そこで今回は、貯金2,000万円の必要性や2,000万円を貯めている割合、貯めるまでの方法について解説します。
■2,000万円の貯金は必要か?
すべての人が2,000万円を貯めなければならないわけではありません。単身世帯で年金以外の収入がある場合、2,000万円の貯金は必要ないでしょう。
反対に2人世帯で老後の収入が年金だけであれば、生活レベルによっては2,000万円以上の貯金が必要だということがわかっています。
※ちなみに
「貯金」と「預金」の違いはお金を預ける金融機関の違いです。大きく下記2つに分けることができます。本記事ではどちらの場合も「貯金」という言葉を使って説明します。
- 貯金:ゆうちょ銀行、JAバンク、JFマリンバンクなどにお金を預ける場合
- 預金:銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などにお金を預ける場合
■2,000万円を貯蓄(金融資産を保有)している人の割合
では、実際に2,000万円を貯蓄している人はどの程度いるのでしょうか。
ここでは、単身世帯と2人以上の世帯に分け、年齢別や年収別、地域別に2,000万円以上の金融資産を保有している割合を紹介します。
●年齢別
《年齢別2,000万円以上の金融資産を保有している人の割合》
| 単身世帯 | 2人以上の世帯 | |
|---|---|---|
|
20歳代 |
0% |
2.9% |
|
30歳代 |
7.1% |
6.6% |
|
40歳代 |
8.6% |
11.8% |
|
50歳代 |
13.7% |
16.6% |
|
60歳代 |
23.1% |
30.0% |
|
70歳代 |
25.5% |
27.1% |
- 引用1:各種分類別データ(令和5年) ― 家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)|知るぽると(Excelデータのタブ[4]の表より)

- 引用2:各種分類別データ(令和5年) ― 家計の金融行動に関する世論調査[2人以上世帯調査](令和3年以降)|知るぽると(Excelデータのタブ[4]の表より)

- ※上記データの「2,000万円以上3,000万円未満」「3,000万円以上」を足し合わせた割合
年代が上がっていくにつれて、2,000万円以上の金融資産を保有している割合も増加していることがわかります。また単身世帯よりも2人以上の世帯のほうが2,000万円以上の金融資産保有率が高い傾向があります。
●年収別
次に年収別の割合を見てみましょう。
《年収別2,000万円以上の金融資産を保有している人の割合》
| 単身世帯 | 2人以上の世帯 | |
|---|---|---|
|
300万円未満 |
10.8% |
8.5% |
|
300万~500万円未満 |
13.7% |
15.3% |
|
500万~750万円未満 |
26.9% |
19.1% |
|
750万~1,000万円未満 |
65.5% |
26.6% |
|
1,000万~1,200万円未満 |
9.1% |
39.3% |
|
1,200万円以上 |
54.5% |
43.1% |
- 引用1:各種分類別データ(令和5年) ― 家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)|知るぽると(Excelデータのタブ[4]の表より)

- 引用2:各種分類別データ(令和5年) ― 家計の金融行動に関する世論調査[2人以上世帯調査](令和3年以降)|知るぽると(Excelデータのタブ[4]の表より)

- ※上記データの「2,000万円以上3,000万円未満」「3,000万円以上」を足し合わせた割合
2人以上の世帯は、年収が上がれば2,000万円以上の金融資産を保有している割合も上がる傾向がありますが、単身世帯では「年収1,000万~1,200万円未満」で割合が大きく9.1%と減少します。
●地域別
2,000万円以上の金融資産を保有している割合は、地域によっても異なります。
《地域別2,000万円以上の金融資産を保有している人の割合》
| 単身世帯 | 2人以上の世帯 | |
|---|---|---|
|
北海道 |
7.0% |
15.6% |
|
東北 |
8.7% |
14.1% |
|
関東 |
15.0% |
20.6% |
|
北陸 |
10.8% |
23.5% |
|
中部 |
17.1% |
18.7% |
|
近畿 |
12.9% |
19.7% |
|
中国 |
12.3% |
17.4% |
|
四国 |
10.0% |
22.3% |
|
九州 |
10.4% |
14.8% |
- 引用1:各種分類別データ(令和5年) ― 家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)|知るぽると(Excelデータのタブ[4]の表より)

- 引用2:各種分類別データ(令和5年) ― 家計の金融行動に関する世論調査[2人以上世帯調査](令和3年以降)|知るぽると(Excelデータのタブ[4]の表より)

- ※上記データの「2,000万円以上3,000万円未満」「3,000万円以上」を足し合わせた割合
地域によって割合に幅がありますが、北陸地方の2人以上の世帯が23.5%と高くなっている点は注目すべきでしょう。
また全体的に、単身世帯より2人以上の世帯のほうが2,000万円以上の金融資産を保有している割合が大きい傾向にあります。
■2,000万円を貯める方法
2,000万円を貯める方法としては、以下のものが挙げられます。それぞれの方法について詳しく解説します。
●先取り貯金
先取り貯蓄とは、文字どおり給与などの収入が入った際に、まず決まった額を"先取り"で貯金に回し、残った金額で生活することです。
自分で貯金する分を引き出し、貯蓄用口座に入れる方法もありますが、給与口座から自動で振込む機能を使えば手間も省けます。その際の貯蓄用口座は、できるだけ引き出せないように、あえてキャッシュカードを作らないなど工夫しておきましょう。
いつでも引き出せる状態だと、つい生活費の不足分にあててしまい、先取り貯蓄の意味がなくなってしまいます。
●家計簿の活用
家計簿をつけることで毎月の収支状況がわかるほか、どのようなものにどれくらい支払っているのかを把握できます。お金を使いすぎ、というときは買い物などをセーブすることを意識できるでしょう。
また、家計簿をつけることと同様に貯蓄簿を活用することもおすすめです。貯蓄は先取り貯蓄だけでなく、ボーナスなどの臨時収入が入ったときも行うことができます。貯蓄簿で管理して、現在いくら貯蓄があるのかを把握できればモチベーションも高まるでしょう。
近年は、家計簿アプリのサービス内容も充実しており、さまざまな金融機関と連携できるようになっています。またクレジットカードやネットショッピングサイトなどとも連携でき、いつ・いくら何に使ったかが一目で把握しやすいでしょう。
●家計の見直し
家計の見直しは、無駄な支出を抑えるための最も有効な手段です。家計の見直しを行う際には、まず固定費から見直しましょう。
固定費とは、家賃や通信費、光熱費などのことで、なかでも通信費を見直すことで大きな節約につながるケースが見られます。「通信費が高い」と感じた場合は、キャリアを見直してもいいでしょう。
また近年は、スマートフォンで有料のアプリに簡単に課金できます。本当に有料のサービスが必要かを考えたうえで、必要なければ解約を検討してもいいでしょう。同じことが有料動画や音楽配信サイトへの課金でもいえます。
金額は、月単位で考えると少額でも年単位にするとまとまった額になります。契約はしたもののあまり利用していないサブスクのサービスがある場合は、解約してしまいましょう。
ここで重要なのは、解約のタイミングです。例えば「年契約しているから次の更新時に解約しよう」などと先送りしても、うっかりと忘れてしまうことも少なくありません。そのため不要だと思った時点で、もったいないと思い切って解約するのもよいでしょう。
●収入を増やす
無駄な支出を抑えると同時に収入を増やすことも考えてみましょう。
得意分野があるのであれば、それを活かして収入を得る方法を考えてみてはいかがでしょうか。例えば手先が器用な人なら雑貨をつくって売る、といった方法もよいかもしれません。
家でできる仕事であれば、時間に束縛されずにできるためおすすめです。断捨離を考えている場合は、フリマアプリで不用品を売ることで収入を得られます。
ただし方法によっては、一定の所得金額に達した場合に確定申告が必要になる可能性があるため、忘れずに行うようにしましょう。(断捨離で不用品を売る場合は非課税)
■2,000万円を貯めるための資産形成方法
2,000万円を貯めるための資産形成方法にはさまざまなものがあります。ここでは、投資のほか、投資を行うにあたって利用したい制度について紹介します。
●投資(株式・投資信託など)
貯蓄として単に銀行へ預金しているだけでは、なかなか増えません。せっかく貯蓄しているなら、そのお金を投資して働いてもらいましょう。
投資商品には、株式や債券、投資信託などがあります。投資を行ううえでの原則は、「長期にわたって」「積み立てながら」「分散して」行うことです。
投資信託を選べば、1本に投資するだけでも分散が自動的に行えるため、投資経験がない場合は、まず投資信託から始めてみましょう。株式は、原則100株単位で購入する必要があるため、基本的にはまとまった費用が必要です。
また投資した会社の経営状況によっては株価が下がる可能性があるほか、倒産してしまうと株の価値はなくなります。
株式投資には、大別すると「値上がり益を期待して投資する方法」「分配金を期待して投資する方法」の2種類がありますので、どちらかの方法を優先しながら投資してもいいでしょう。
債券とは、最初から利率が決まっていて、満期まで保有していれば利息と投資元本が受け取れる商品です。ただし、途中で解約すると元本割れのリスクがあるため注意しましょう。
また債券には、国内だけでなく海外の債券もあります。ちなみに投資で受け取れる収益を「リターン」といい、値動きの幅を「リスク」といいます。
リターンとリスクは、正比例の関係にあるため、リターンが大きい投資商品ほど値動きの幅が大きくなる傾向です。リターンとリスクが小さい商品の代表的なものが債券で、株式はリターンが大きくリスクも大きくなります。また国内の投資商品よりも海外の投資商品のほうがリターンおよびリスクが大きくなる傾向です。
これらのことを意識しながら、値動きの異なる投資商品を組み合わせたり、リターンやリスクの大きい商品と小さい商品を組み合わせたりした運用を考えましょう。
●新NISAの活用
新NISAとは、2024年から始まった制度です。NISA口座を介して取引した金融商品は、毎年360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)まで、そして最高1,800万円(生涯投資枠)までの運用益が非課税になります。
運用期間は恒久的で、日本国内在住で18歳であれば始められるため、運用を検討している場合はぜひ利用しましょう。
また、つみたて投資枠で購入できるのは主に投資信託となっており、株式を購入したい場合は成長投資枠で購入する必要があります。通常運用益には20.315%(復興特別所得税を含む)が課税されるため、それが非課税になる点は大きいでしょう。
●iDeCoの活用
iDeCoとは、私的年金の一つで原則60歳まで加入できます。ただし1度加入すると、基本的に60歳まで脱退できません。その仕組みから、老後資金を貯めるための方法として利用している人が多くみられます。
ただし、iDeCoの掛け金は、全額所得控除の対象になるほか、運用益は非課税、受取時も受取方法に応じた控除が受けられるメリットがあるため、新NISAと併用することをおすすめします。
●変額保険の利用
変額保険とは、終身保険の一つで契約者が保険料を払いながら運用商品(特別勘定といいます)を選びながら運用していく保険です。
運用商品は、主に投資信託に限られますが、運用成績によって保険金額が変動する点が大きな特徴です。ただし基本保険金額が設定されており、変額保険加入中に亡くなった場合の保険金額が基本保険金額よりも低い場合は、基本保険金額が支払われます。
満期保険金は、運用成績によって異なり基本保険金額より低くても運用成績に応じた満期保険金が支払われるため、満期を設定している場合は満期が近くなるにつれて運用商品を安定運用に変更するなどの工夫が必要です。変額保険の保険料は、生命保険料控除の対象になるため、「保険を活用して保障も得ながら運用したい」と考えている人におすすめです。
■まとめ
平均寿命の延びや医療費の増加、さらに物価上昇などを考えると、老後生活を送るためには目安として2,000万円以上の貯蓄が必要だと認識しておきましょう。
そのうえで現在の貯蓄がいくらあるのか、また家計を見直すことにより貯蓄に回せるお金がないかを考えてみましょう。貯蓄を検討しているだけではなく、運用を取り入れることも大切です。
徐々に環境は変化しているものの、低金利状況下の場合、単に銀行へ預金しているだけではなかなか資産は増えていきません。運用には、さまざまな種類があり、それぞれに特徴も異なります。また運用を行う際は、新NISAやiDeCoなど非課税で行える制度もあるため、上手に活用しながら資産形成を行いましょう。