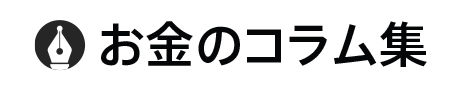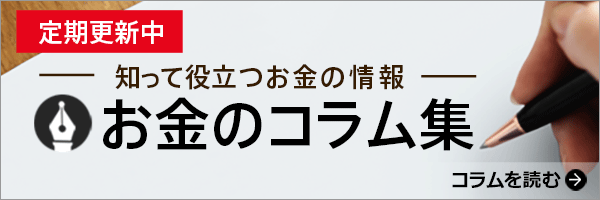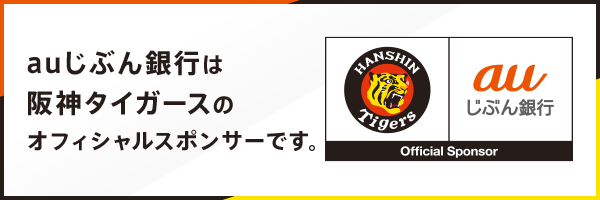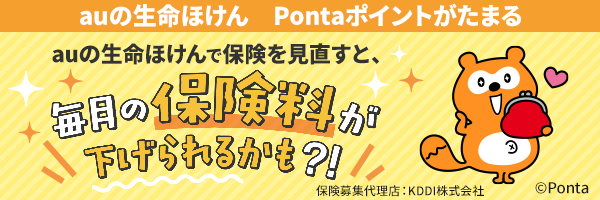2024/12/27
利上げとは何? 今更聞けない人のためにわかりやすく解説
執筆者:馬場愛梨(ファイナンシャル・プランナー)

近年、ニュースなどで「利上げ」という言葉をよく耳にするようになりました。利上げは経済や私たちの暮らしにも影響を及ぼすものですが、「利上げとは何なのか、どんな意味があって具体的にどのように影響するのか、実はよくわからないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、利上げの意味や影響について、初歩的な内容も含めて経済に馴染みがない人にもわかりやすく説明します。
■「利上げ」とは? どういう意味?
「利上げ」とは、中央銀行が政策金利を引き上げることを指す言葉です。
中央銀行は、その国や地域の金融の中核となる機関です。お金(紙幣や貨幣)を発行したり、物価を安定させるための金融政策を行ったりする権限を持っていて、日本では「日本銀行(日銀)」がその役目を担っています。
中央銀行が金融政策の一環で設定する金利のことを「政策金利」といいます。政策金利が上がると、民間の金融機関(銀行など)が設定する金利も上昇します。
金利は、お金の貸し借りをするときに発生する利息の割合です。つまり、利上げによって民間の金融機関の金利が上がると、企業や個人がお金を借りる際の返済額が増えることになります。
利上げを行うと、景気や物価、為替をはじめ広い範囲に影響が出ます。ローンを組んでいる(組む予定がある)人や投資を行っている人はもちろんですが、それらに縁がなく経済に馴染みがない人でも、利上げによって日々の暮らしに影響が出る可能性は十分あります。
●利上げの目的は? なぜ必要?
前述の通り、利上げが行われると、お金を借りた際の借金の返済が大変になります。では、なぜ利上げを行うのでしょうか。
実は利上げには、景気の過熱や物価の上昇を抑える効果があります。あえてお金を借りにくくし、経済活動を行いにくくすることで、「買いたい」という人を少なくして(需要を抑えて)物価を下げるのです。
日銀は「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資すること」を理念としています。景気や物価が上がり過ぎたり下がり過ぎたりすると人々が暮らしにくくなるため、そうならないよう、経済や市場の動向を見ながら通貨や金融を調節します。
●利上げは誰がどうやって決める?
利上げは金融政策の一環ですが、政府が決めるわけではありません。
日本では、中央銀行である日銀が「金融政策決定会合」での審議を経て決定します。この会合は年8回開催され、日銀の総裁(1人)、副総裁(2人)、審議委員(6人)の計9人で多数決を取ります。
会合ごとの参加者や議論の概要、今後の経済・物価の展望などは、日銀の公式サイト上で公開されており、いつでも誰でも確認することができます。
ちなみに、アメリカでは中央銀行にあたるFRB(Federal Reserve Board:米連邦準備制度理事会)がFOMC(Federal Open Market Committee:連邦公開市場委員会)という会合の中で利上げなどを決定します。ユーロ圏ではECB(European Central Bank:欧州中央銀行)の政策理事会など、国や地域ごとに同様の機関や会合が存在します。
●「利下げ」もある
政策金利を上げることが「利上げ」ですが、逆に政策金利を下げる「利下げ」もあります。両者は効果が正反対で、行われる目的も異なります。以下の表で違いを確認しましょう。
【利上げと利下げの比較】
| 利上げ | 利下げ |
|---|---|
|
政策金利を上げる |
政策金利を下げる |
|
企業や個人がお金を借りにくくなる |
企業や個人がお金を借りやすくなる |
|
経済活動が抑制される |
経済活動が活発になる |
|
景気の過熱を抑える |
景気を過熱させる |
|
物価の上昇を抑える |
物価の下降を抑える |
|
金融引締め政策 |
金融緩和政策 |
利上げは景気や物価を抑える効果があり、「金融引締め政策」と呼ばれています。一方、利下げは景気や物価を上昇させる効果があり、「金融緩和政策」と呼ばれています。
■利上げするとどこにどのような影響が出る?
利上げが行われるとどうなるのか、自分にも関係があるのか、と気になる人もいるでしょう。利上げが及ぼす影響について具体的に見ていきます。
●物価 : 下がる
利上げは、景気や物価を抑えるために行われます。そのため、利上げが行われると、通常は物価が下がります。
基本的には、利上げによって民間金融機関の金利が上がる→お金を借りにくくなる→物を買いにくくなる→需要が減少して価格が下がるといった流れで影響が出ます。後述しますが、利上げによる為替の変動の影響で、輸入がしやすくなって物価が下がることもあります。
●株価 : 下がる
利上げが行われると、経済活動が抑制されます。企業にとっては物が売れにくくなり、設備投資もしにくくなり、業績が上がりにくくなります。そのため、株価も下落する傾向があります。
その他、利上げの仕方によっては景気が悪くなったり、賃金が上がりにくくなったりすることもあります。
●為替 : 円高になる
利上げが行われると、為替にも影響が出ます。ここでいう為替とは、異なる通貨同士を交換する際の比率(レート)のことです。為替は常に変動していて、需要が多い(欲しいと思う人が多い)通貨が高くなる仕組みです。
金利が低い国の通貨よりも高い通貨のほうが投資家から見て魅力的なので、お金は金利が低いところから高いところに流れていく傾向があります。
例えば、日本が利上げを行った(もしくはアメリカが利下げを行った)場合、両国間の金利差が縮小して日本にお金が流れる、つまりドルを売って円を買う動きが強まるため「円高ドル安」となることが多い傾向にあります。
●個人の暮らしへの影響(マイナス面)
利上げが行われると経済活動が抑制されるため、基本的に景気が悪くなります。物が売れにくくなって企業の業績が上がりにくくなり、結果として、給料がなかなか上がらない人や就職できない人が増えます。そうなると「お金を使わずに取っておこう」と思う人が多くなり、さらに経済が回りにくくなります。
また、前述のとおり株価が下がる傾向があるため、株式や投資信託への投資を行っている人は利益を出しにくくなる場合があります。
さらに、政策金利が上がると民間の金融機関の金利も上がります。個人の暮らしに特に影響があるのは「住宅ローン」でしょう。住宅ローンの金利が上がれば、その分返済額が増えます。これから住宅ローンを組もうとしている人や、変動金利型の住宅ローンを組んでいる人は注意が必要です。
変動金利型の住宅ローンは、利上げが行われると金利が上がります。固定金利型(利上げがあっても金利が変わらないタイプ)より元の金利が低めに設定されていることが多いのですが、いつどれくらい金利が変動するかがわからないことはリスクといえます。
近年は低金利の状態が続いていましたが、その中でギリギリ返済できるレベルの変動金利型のローンを組んでいる場合、利上げが行われると返済額が増えて家計を圧迫し、返済が困難になる可能性があります。
●個人の暮らしへの影響(プラス面)
利上げによる影響は、マイナス面ばかりではありません。良いこともあります。
まず、物価が下がることで、買い物がしやすくなります。「昨今の物価高で生活が苦しくなった」という人は多いでしょう。利上げの結果、食料品や日用品の値段が下がれば出費を抑えられます。
また、利上げが行われると、民間の金融機関の預金金利が上がります。預金金利は「預けたお金がどれくらい増えるか」を示すもので、上がれば上がるほどお金が増えやすくなります。
住宅ローンなど、お金を借りる場合の利上げは不利ですが、お金を預ける(貸す)場合には利上げは有利に働きます。
■日本や海外の利上げの動向
景気や物価を調整するための利上げ(利下げ)は、世界各国で行われています。直近ではいつどこでどれくらい行われ、どのような影響があったのか見ていきましょう。
●日本の金融政策
2016年以降、日本では政策金利が「-0.1%」と非常に低く、「マイナス金利」と呼ばれる状態が続いていました。マイナス金利は過去に例がないほどの低金利で、世界的に見てもまれで「異常」とも呼べる状態でした。
しかし2024年3月、ついにマイナス金利の解除が決定され、新たな政策金利は「0~0.1%程度」となりました。実に17年ぶりの利上げでした。その後、同年7月には追加の利上げが決定し、政策金利は「0.25%程度」とされました。
この利上げにより、預金金利や住宅ローン金利に影響が出始めています。今後のローン返済に不安を覚える人もいるでしょう。
しかし住宅ローンの多くは、金利が上がっても5年間は1回あたりの返済額が変わらない、いわゆる「5年ルール」があります。日銀の植田総裁は「その5年間で賃金が先に上がり、返済額はその後に上がるので、負担は大きく軽減される」という認識を示しています。
●アメリカの金融政策
アメリカは世界トップクラスの経済大国です。その動向は国内だけにとどまらず、世界全体の経済にも影響を及ぼします。特に、日本はアメリカと経済的に深いつながりがあるため、より影響を受けやすいでしょう。
アメリカでは、日本よりもダイナミックに利上げ・利下げが行われています。2021年頃からインフレ(物価上昇)が続いていて、それを抑えるためにゼロ金利(政策金利0%)が解除され、計10回以上利上げが行われてきました。
しかし、直近では2024年9月に0.5%の利下げを行い、同年11月7日にはさらに0.25%の利下げを決定し、政策金利は「4.5~4.75%」となりました。
FRB(アメリカの中央銀行にあたる組織)のパウエル議長は「あまりに急に利下げをするとインフレの改善が妨げられる一方、ゆっくり過ぎると経済活動や雇用を過度に弱めかねない」といった趣旨の発言をしています。経済の動向を注視しながら、その都度判断が行われることになりそうです。
■利上げに備えてやっておくことは?
今後、日本ではさらなる利上げが行われる可能性があります。利上げに備えるとしたら、具体的に何をどうすればよいのでしょうか。
●住宅ローンの組み方を考える
まず、住宅ローンを変動金利で組んでいる人や、住宅ローンをこれから組む予定の人は、利上げの影響を受ける可能性が高いので注意が必要です。
すでに借りている人は、返済額が上がっても返済に困ることがないよう、家計を整理してみましょう。金利上昇によって返済額がいくらになるのか、0.5%上がった場合、1.0%上がった場合などいくつかのパターンに分けて試算してみると、家計がどれくらい圧迫されるかがわかります。固定金利との差額分を貯蓄しておくことも有効な対策です。
これから住宅ローンを組む予定の人は、変動金利だと上がる可能性があることを認識した上で、余裕のある組み方をすることが大切です。たくさん借りるほど返済が大変になるので、変動金利で借りる場合でも借入額は「固定金利で借りたとしても問題なく返済できる金額」を目安に決めるなど、工夫しましょう。
●資産運用を検討する
個人の暮らしは金利や物価、景気、為替などに左右されます。経済的な安定を手に入れるためには、どう転んでも問題ないよう資産づくりを進めておくことが大切です。
日本だけでなく海外にもお金を配分する、株式だけでなく債券にも投資する、投資先は1つの業種に絞らず複数にするなど、分散を心がけるとリスクを抑えられます。景気が悪くなったり株価が下がったりしても、あせらず上昇を待ちましょう。
■まとめ : 利上げは景気や物価、日々の暮らしに直結する
利上げとは、中央銀行が政策金利を上げることです。利上げが行われると景気が抑制されたり、物価が下がったり、為替が変動したりするなどさまざまな影響が出ます。
利上げは住宅ローンや預金、投資など、私たちの暮らしにも大きな影響を及ぼすため、「関係ないこと」「遠い世界の話」ではなく自分事として捉えることが大切です。ニュースなどで取り上げられていたら、ぜひ注目しましょう。