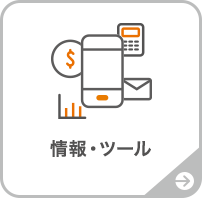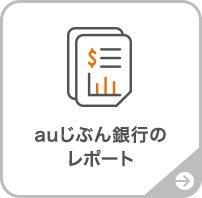更新日 : 2025年12月28日
今週の見通し
2025年12月29日~2026年01月09日(154.00円~159.00円)
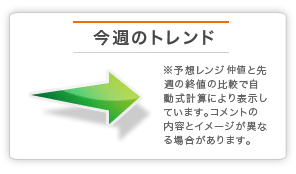
- 下げ渋りか、12月米雇用統計などが手掛かり材料に
- 下げ渋りか。米国の金利安観は後退していないものの、直近の米経済指標で7-9月期米国内総生産(GDP)は予想外に強かったことが意識されそうだ。1月5日発表の12月ISM製造業景況指数や9日に発表される12月雇用統計を見極める展開となり、リスク回避的なドル売り・円買いはある程度抑制されるだろう。
先週の動き
2025年12月22日~2025年12月26日(155.56円~157.75円)
- 弱含み、米国金利の先安観でドル売り強まる
- 弱含み。トランプ米大統領は米連邦準備制度理事会(FRB)の次期議長人事を巡って「政策金利引き下げを望む」と要請したことを受けて2026年も利下げが行われる可能性が高まり、ドルは弱含みとなった。日本銀行の植田総裁は講演で「現在の実質金利は極めて低水準」と指摘したことも材料視されたようだ。
バックナンバー
2025年12月15日~2025年12月19日の動き
- 上昇、日本の財政悪化を警戒して円売り強まる
- 上昇。12月18-19日開催の金融政策決定会合で0.25ptの追加利上げが全会一致で決定されたが、日本の来年度予算で一般会計の歳出総額は120兆円を超える見通しであるため、財政悪化を懸念した円売りが活発となった。日本銀行の利上げペースが加速する可能性は低いことも米ドル買い・円売りを促した。
2025年12月08日~2025年12月12日の動き
- 強含み、米長期金利高止まりでドル売り弱まる
- 強含み。12月9、10日に開かれた米連邦公開市場委員会(FOMC)の会合で0.25ptの追加利下げが決定されたが、来年以降の米政策金利見通しは引き続き不透明であること、米長期金利の高止まりが意識されたことから、リスク選好的な米ドル買い・円売りが続いた。日本の財政悪化も警戒されたようだ。
2025年12月01日~2025年12月05日の動き
- 弱含み、日銀12月利上げの可能性高まる
- 弱含み。日本銀行の植田総裁は12月1日、今月の会合で「利上げの是非について適切に判断したい」と述べ、政策金利を引き上げる可能性を示唆した。さらに、高市政権が今月の利上げを容認する姿勢であることが複数の関係者へのマスコミ取材で明らかになり、12月利上げを想定した米ドル売り・円買いが活発となった
更新日 : 2025年12月28日
今週の見通し
2025年12月29日~2026年01月09日(182.50円~186.00円)
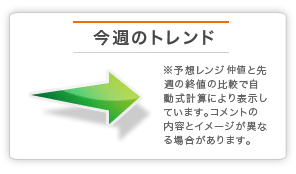
- 下げ渋りか、日本の財政悪化への懸念残る
- 下げ渋りか。欧州中央銀行(ECB)は来年の利上げについて明確にしていないため、ユーロは買いづらい。一方、高市政権は円安牽制の姿勢を強めており、リスク選好的なユーロ買い・円売りは抑制されそうだ。ただ、日本の財政悪化への懸念は消えていないため、ユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いと予想される。
先週の動き
2025年12月22日~2025年12月26日(183.28円~184.92円)
- 伸び悩み、日銀は2026年も利上げ継続の可能性
- 伸び悩み。週初に185円に迫る場面があったが、日本政府による為替介入が警戒されたことや日本銀行は2026年も複数回の利上げを行うとの思惑でリスク選好的なユーロ買い・円売りは縮小。欧州中央銀行(ECB)が来年中に利上げを開始するとの見方がやや後退したこともユーロ買い・円売りを抑制したようだ。
バックナンバー
2025年12月15日~2025年12月19日の動き
- 強含み、日欧金利差の縮小予想は後退
- 強含み。184円台後半まで上昇し、一段高となった。日本銀行による追加利上げは織り込み済みだったことから、利上げ決定後にリスク選好的なユーロ買い・円売りが拡大した。日欧金利差の縮小予想は後退し、欧州中央銀行(ECB)は来年中に利上げを開始するとの市場観測もユーロ買い・円売りを促したようだ。
2025年12月08日~2025年12月12日の動き
- 堅調推移、ECBは来年後半にも利上げ開始の可能性浮上
- 堅調推移。一時183円台前半まで上昇した。日本銀行による12月利上げの可能性が高まったものの、欧州中央銀行(ECB)は来年後半にも利上げを開始するとの市場観測が広がり、リスク選好的なユーロ買い・円売りが活発となった。日本財政の悪化に対する懸念は消えていないこともユーロ買い・円売り促したようだ。
2025年12月01日~2025年12月05日の動き
- 伸び悩み、日銀12月利上げの可能性高まる
- 伸び悩み。週前半より、日本銀行による12月利上げの可能性が高まり、ユーロ圏と日本の金利差縮小を想定したユーロ売り・円買いが広がった。ただ、日本財政の悪化に対する市場の懸念は残されており、週後半にかけてリスク回避的なユーロ売り・円買いはやや一服。米ドル安・円高が一服したことも影響したようだ。
更新日 : 2025年12月28日
今週の見通し
2025年12月29日~2026年01月09日(103.50円~106.50円)
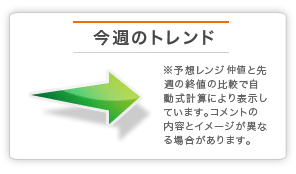
- もみ合いか、11月CPIが手掛かり材料に
- もみ合いか。1月7日発表の11月消費者物価指数(CPI)が有力な手掛かり材料となりそうだ。インフレ率は10月実績を下回る見込みだが、豪準備銀行(中央銀行)の政策金利見通しに影響を及ぼす可能性は低いとみられる。一方、日本の為替介入に対する警戒感は消えておらず、豪ドル買いが一段と強まる可能性は低い。
先週の動き
2025年12月22日~2025年12月26日(103.83円~104.93円)
- 堅調、将来的な利上げの可能性浮上
- 堅調。日本銀行は2026年も利上げを継続する可能性が高まり、リスク選好的な豪ドル買い・円売りが弱まる場面があった。しかし、豪準備銀行(中央銀行)が2026年中に利上げを開始するとの見方が浮上したほか、米国金利の先安感が強まったことで、その後に豪ドル・円は買い優勢となる。
バックナンバー
2025年12月15日~2025年12月19日の動き
- もみ合い、日銀利上げ後の円安で下げ渋る
- もみ合い。豪準備銀行(中央銀行)の政策金利は長期間据え置きとなる可能性が高まった。一方、日本銀行は12月19日、0.25%の利上げを決定したが、事前に織り込まれていたほか、利上げペース加速の可能性は低いとの見方も強まり、利上げ決定後には円売りが優勢。豪ドル・円は下げ渋った。
2025年12月08日~2025年12月12日の動き
- 上昇、将来的な利上げの可能性浮上
- 上昇。12月9日開催の理事会で政策金利の据え置きが決まったが、インフレ持続を受けて将来的な利上げの可能性が浮上した。11日発表の11月雇用統計で雇用者数は予想外に減少したものの、円相場が他の通貨に対して弱含んだこともあり、豪ドル・円は堅調な動きが続いた。
2025年12月01日~2025年12月05日の動き
- もみ合い、7-9月期経済成長率は前期実績を上回る
- もみ合い。12月3日発表の7-9月期国内総生産(GDP)は前年比2.1%増となり、前期の成長率を上回った。こちらは豪ドル買いの要因となっている。一方、植田総裁講演を受けて日本銀行による12月利上げの可能性が高まったことは、豪ドル・円の上値抑制要因となった。
更新日 : 2025年12月28日
今週の見通し
2025年12月29日~2026年01月09日(9.20円~9.50円)
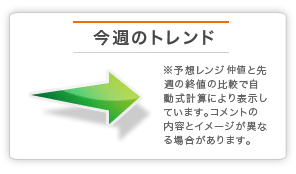
- もみ合いを予想、引き続き材料難の展開を想定
- もみ合いを予想。年末年始の2週間とはいえ、手掛かり材料が乏しいことで、現在のランド・円水準が大きく変化する可能性は乏しいように感じる。日本の年末年始休暇中の円安進行の可能性などは残るが、一段の円安場面ではさすがに介入警戒への意識も強まり、円の下支えとなろう。
先週の動き
2025年12月22日~2025年12月26日(9.31円~9.43円)
- もみ合い、手掛かり材料乏しく小動きに終始
- もみ合い。欧米市場のクリスマス休暇入りもあって、ランド・円相場は小動きに終始した。円は対ドルに対して、週前半に反動高の形となったが、週後半にかけては再度軟化方向になっている。ランドにとっては、金価格の高騰などは支援材料になったと考えられる。
バックナンバー
2025年12月15日~2025年12月19日の動き
- 上昇、日銀利上げ決定後の円安進行で
- 上昇。日本銀行が12月19日に政策金利の引き上げを決定したが、想定通りの動きでもあり、その後の為替市場では円安が進む展開に。ランド・円の上昇にもつながった。また、南アフリカの順調なインフレの落ち着きも、ランドへの資金流入を促すことになっているようだ。
2025年12月08日~2025年12月12日の動き
- もみ合い、大きな手掛かり材料に乏しく
- もみ合い。先週は目立った手掛かり材料も乏しく、ランド・円の動きは小幅にとどまる格好となった。日本銀行の利上げ観測は高まる方向となっているが、先週は円相場が他通貨に対して相対的に軟調な推移となっており、ランド・円はやや上昇する形にはなった。
2025年12月01日~2025年12月05日の動き
- もみ合い、堅調な景気動向支え
- もみ合い。12月1日の植田総裁講演を受けて、日本銀行の12月利上げ観測が一気に台頭、ランド・円の下落要因に。ただ、南アフリカの7-9月期国内総生産(GDP)は4四半期連続でのプラス成長を達成しており、堅調な景気動向がランドの下支え要因となっている。
更新日 : 2025年12月28日
今週の見通し
2025年12月29日~2026年01月09日(90.50円~91.50円)
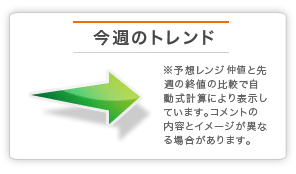
- もみ合いか、NZの利上げの可能性を見極める展開へ
- もみ合いか。NZ準備銀行(中央銀行)による利上げの可能性と日本政府・日本銀行による円買い介入の可能性を見極める形でNZドルは対円でもみ合う展開となりそうだ。1月23日発表のNZ10-12月消費者物価指数は下振れる可能性が高く、NZの利上げ観測に一定の歯止めをかける可能性があることに留意しておきたい。
先週の動き
2025年12月22日~2025年12月26日(90.60円~91.06円)
- 上昇、NZ利上げ意識でNZドル買いが優勢に
- 上昇。NZ準備銀行(中央銀行)のブレーマン総裁が必要に応じて金融政策を調整すると発言して以降、市場ではNZの利上げの可能性が意識されている。その一方、日本政府の円安牽制を機に日本政府・日本銀行による円買い介入の可能性が市場で意識されている。前者が後者より強く意識され、対円でNZドルは週間で上昇した。
バックナンバー
2025年12月15日~2025年12月19日の動き
- 弱含み、週前半の利益確定売りが響く
- 弱含み。利下げ打ち止め観測で前週まで3週連続で買われていたNZドルは、週後半の日本銀行の金融政策決定会合を控えた週前半に対円で大きく売られた。週半ばからNZドルは買い戻され始め、追加利上げに一段の積極姿勢を示さなかった日銀の植田総裁発言で週末に円売りが強まった。週間ではNZドルが対円で弱含みに。
2025年12月08日~2025年12月12日の動き
- 上昇、NZ利上げ観測を織り込む動きが台頭した模様
- 上昇。NZと日本の金利差は大きいままのため、NZ準備銀行(中央銀行)が11月下旬の理事会で示唆した利下げ打ち止めの可能性を織り込む形でNZドル買い優勢の状況が続いている。そこへ同行総裁発言で2026年のNZ利上げの可能性が市場で意識されたようだ。対円で買いが強まり、NZドルは週間で上昇した。
2025年12月01日~2025年12月05日の動き
- やや弱含み、日銀による継続的な追加利上げ観測で円買い優勢
- やや弱含み。米国で労働市場の減速傾向が確認され、継続的な追加利下げ観測が緩やかに強まる方向となった。これで為替市場のリスク選好が緩やかに強まる方向となり、NZドル買いを支援。反面、日本銀行による継続的な追加利上げ観測が円買いを支援した。週間では対円でNZドル売りがやや優勢となり、やや弱含みに。
更新日 : 2025年12月28日
今週の見通し
2025年12月29日~2026年01月09日(27.80円~29.00円)
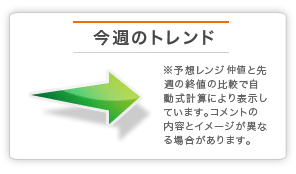
- 慎重ムードか、製造業PMIなどに注目
- 期間内に12月のS&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)などが発表されるため、慎重ムードになると予測される。強弱材料では、中国の景気対策への期待感などが引き続き支援材料へ。また、成長予想の上方修正も引き続き好感されよう。半面、円高が進行した場合、対円レートは下落も。
先週の動き
2025年12月22日~2025年12月26日(27.83円~28.51円)
- 弱含み、円高進行などが足かせ
- 弱含み。円高進行が対円レートを押し下げた。また、週後半はクリスマス休暇で多くの市場が休場となるため、積極的な買いは手控えられた。半面、レアルの下値は限定的。成長予想の上方修正が好感されたほか、米追加の利下げ観測などが支援材料となった。
バックナンバー
2025年12月15日~2025年12月19日の動き
- 反落、株安や弱い経済指標で
- 反落。株式市場の下落がレアル需要を縮小させた。また、弱い経済指標も圧迫材料。10月の経済活動指数の上昇率(前年同月比)は0.38%となり、前月の改定値2.20%と予想の0.65%を下回った。半面、米追加の利下げ観測がレアルの支援材料となった。また、円安進行も対円レートをサポートした。
2025年12月08日~2025年12月12日の動き
- 強含み、米利下げ決定などが支援材料
- 強含み。米利下げの決定がレアルなど新興国通貨の支援材料となった。また、円安進行も対円レートをサポート。ほかに、経済指標の改善が好感された。10月の小売売上高が前年同月比で1.1%上昇し、前月の0.8%と予想の0.0%を上回った。半面、原油価格の大幅下落がレアルの上値を押さえた。
2025年12月01日~2025年12月05日の動き
- 反落、円高進行や成長鈍化などが圧迫材料
- 反落。円高進行が対円レートを押し下げた。また、成長鈍化も嫌気された。7-9月期の国内総生産(GDP)成長率は前期の改定値2.4%から1.8%に鈍化。10月の鉱工業生産もマイナス成長に転落した。半面、年内の米利下げ期待の高まりがレアルなど新興国通貨の支援材料となった。
更新日 : 2025年12月28日
今週の見通し
2025年12月29日~2026年01月09日(22.24円~22.50円)
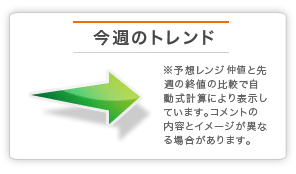
- 横ばいか、円買い介入への警戒感が一服へ
- 横ばいか。日本政府・日本銀行による円買い介入の可能性が意識されやすいことが過剰な円売りへの歯止めをかけ始めているようだ。このため、新たな材料が出なければ、対米ドルで円は横ばい推移になりやすくなっているとみる。こうした中、対米ドル基準値をもとに売買されている人民元も対円で横ばい推移になるとみる。
先週の動き
2025年12月22日~2025年12月26日(22.13円~22.40円)
- やや弱含み、日本政府・日銀の円買い介入への警戒感で
- やや弱含み。先週の為替市場では日本政府・日本銀行による円買い介入を警戒した円買いが日本の財政悪化を警戒した円売りを上回った。このため、対円で米ドルは週間で弱含みとなった。一方、中国人民銀行(中央銀行)が対米ドル基準値高め誘導の姿勢を強化したため、人民元は対円で米ドルほど下げず、週間でやや弱含みに。
バックナンバー
2025年12月15日~2025年12月19日の動き
- 上昇、米ドルに連れ高
- 上昇。日本銀行の追加利上げ観測などで週前半に米ドルは対円で売られた後、週半ばから買い戻された。日本銀行の植田総裁が追加利上げに一段の積極姿勢を見せなかったため、週末に円が急落、米ドルは週間で上昇。中国人民銀行(中央銀行)が対米ドル基準値高め誘導を強化したため、週間で人民元は対円で米ドル以上に上昇。
2025年12月08日~2025年12月12日の動き
- 強含み、対円で米ドルに連れ高
- 強含み。中国人民銀行(中央銀行)が設定する対米ドル基準値に基づいて人民元は売買されるため、米ドルと連動性がある。その米ドルが米労働市場の一定の底堅さが確認されたことなどから対円で買いが優勢となり、やや強含んだ。中国人民銀行の対米ドル基準値高め誘導で人民元は対円で米ドル以上に買われ、週間で強含みに。
2025年12月01日~2025年12月05日の動き
- やや弱含み、米ドルに連れ安
- やや弱含み。対米ドル基準値に基づいて売買される人民元は米ドルとの間に連動性がある。米国で継続的な追加利下げ見通しが強まり、米ドル売り材料となった。一方、日本では継続的な追加利上げ見通しが強まる方向となり、円買い材料となった。対円で米ドルが売られ、追随して人民元も売られ、週間でやや弱含みに。
更新日 : 2025年12月28日
今週の見通し
2025年12月29日~2026年01月09日(10.57円~11.10円)
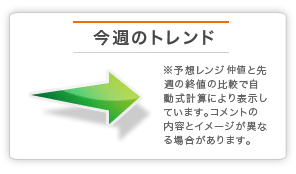
- 見極めるムードか、鉱工業生産などに注目
- 期間内に11月の鉱工業生産などが発表されるため、見極めるムードが強まる見通しだ。強弱材料では、新年のご祝儀相場への期待感からウォンの買いは継続する可能性がある。また、中国の利下げ期待なども引き続き好感されよう。半面、円高が進行した場合、対円レートは下落も。
先週の動き
2025年12月22日~2025年12月26日(10.50円~10.92円)
- 続伸、株高や堅調な米GDP統計を好感
- 続伸。株式市場の上昇がウォン需要を高めた。また、堅調な米国内総生産(GDP)統計も輸出の拡大期待を強めた。ほかに、中国当局が利下げなどに踏み切るとの観測が韓国市場への資金流入が加速すると期待された。半面、弱い経済指標や円高進行がウォンの足かせとなった。
バックナンバー
2025年12月15日~2025年12月19日の動き
- 続伸、円安進行や米追加の利下げ期待で
- 続伸。円安進行が対円レートを押し上げた。また、米追加の利下げ期待もウォンなどの支援材料。ほかに、中国の追加の景気対策への期待感が対中輸出の拡大観測を高めた。半面、株式市場の下落がウォン需要をやや縮小させた。また、世界景気の先行き不透明感なども圧迫材料となった。
2025年12月08日~2025年12月12日の動き
- 強含み、円安進行や米利下げの決定で
- 強含み。円安進行が対円レートをサポートした。また、米利下げの決定もウォンなどの支援材料。ほかに、中国の景気対策への期待感が好感された。中国政府は金融と財政で景気を刺激する方針を明確にした。半面、ウォンの上値は重い。中国のデフレ懸念などが対中輸出の縮小懸念を強めた。
2025年12月01日~2025年12月05日の動き
- 弱含み、円高進行などが足かせ
- 弱含み。円高進行が対円レートの足かせとなった。また、世界景気の不透明感なども圧迫材料となった。半面、ウォンの下値は限定的。年内の米利下げ期待がウォンなどの支援材料。また、国内総生産(GDP、速報)の上振れも好感された。7-9月期のGDP成長率は1.8%となり、前期と予想の1.7%を上回った。

 米ドル
米ドル ユーロ
ユーロ 豪ドル
豪ドル ランド
ランド NZドル
NZドル レアル
レアル 中国元
中国元 ウォン
ウォン